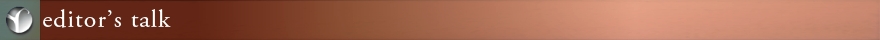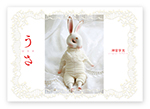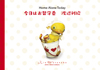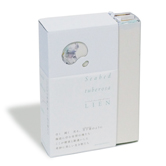stages
十二夜 串田和美演出 シアターコクーン
役者が巧いとか下手だとか
役者が巧いとか下手だとか、感じさせること自体、演出家の責任なんだろうな……とふと思う。
00年代の演劇や飴屋法水の演劇を見ていると、そういうことは感じない。役者というのはまず一生懸命に、巧く演じようとするから、まずそこを止めて、演劇そのものに集中してもらわないとね。
シェークスピアのしかもよく知られている十二夜を演出するのに、フェリーニの映画風に演出してみました、自由劇場みたいに役者が演奏してみました、役者は自由に『十二夜』を思ってください。そうしたらいろいろな面が出てきます。それを観客も自由に楽しんでください……というような演出は、今の時代にいかがなものか。
というか駄目だなぁ。
役者は戯曲を解釈して、それでこれまでの演出と串田がどうちがう演出をするのかを見極めて、それで自分としてはどうそこに対するのかを決めて、稽古でバトルする。その過程を含めて演じるのがシェークスピアだと思う。
オーケストラで演奏するものを即興のフリージャズ風にやってみましょう……というのは意味がない。やるなら新作でやれば良いのだと思う。指揮者がどう解釈して、それをオケがどう受け止めるか、そしてどこで統一感を見いだすのか、あるいは少々、ずれたままでやるのか……再演という行為は、解釈のおもしろさ、さらに言えば、それが今の感覚にどこでつながれるかを見いだす、永遠のトライである。
何十年か前ならともかく、ちょっとこんな風にしました的な演出はまずいなぁ。しかも誰もがフェリーニの映画を思い浮かべてしまうようなコピーの映像的手法は……駄目ですよ。音楽もそれだけでシーンを表現できるほどのものが良いし、映像も台詞を越える何かを伝えるためなら面白いと思う。
ラストの一人二役を、台詞だけで棒立ちで演じさせるのは、松たか子にちょっと酷じゃないかなぁ……。役者がよぉーっしっと燃えるようなハードルなら良いけれど、これじゃぁ困っているのが見え見えだ。
コクーン歌舞伎でも演出を手に入れるのに、だいぶ時間がかかったけれど、今の時代、最初からばしっと見せないと次はないからねぇ。
update2011/01/12