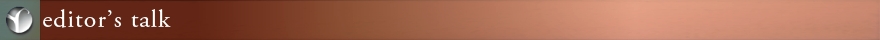stages
『地下室の手記』 イキウメ/カタルシツ
『地下室の手記』の手記
Ⅰ
劇団イキウメは、本公演からはみだすような企画を「カタルシツ」という名称で上演しはじめた。やりたいことを実験的にやる。そんな静かな気合いが伝わってくる。
カタルシツは、「語る」と「室」をカタルシスに引っかけた造語だろう。
やろうとしていることは、朗読ということも関係しているのかもしれない。
パラボリカ・ビスで上演した、指輪ホテルの「断食芸人」(カフカ)の朗読も、不思議な形態をしていた。
朗読はまだまだ開発の余地がある。というか、朗読で実験をする、そんな気分なんだろうな。
シアターカイで勅使川原三郎が踊ったシュルツも、全面、朗読が流れている中だった。
++
さて「カタルシツ」の第一段は、ドストエフスキーの「地下室の手記」。
「地下室の手記」は、地下室に籠ってひたすら社会や友人、自分の周りのあらゆるものに恨み辛みを言い募る自己愛の男のモノローグである。ドストエフスキーが、「罪と罰」「カラマーゾフの兄弟」へ移行する端境期に書かれた、とてつもない暗さと呪詛のようなネガティブさに溢れた異色の作品と言われている。前川知大が現代に置き換えて上演した。
登場人物は、親の遺産で働かなくてすむようになった40歳男(安井順平)と、娼婦( )の二人。
話すなら自分一人についてだけ、地下室のお前のみじめさについてだけにしてくれ。〈俺たち皆〉などと言ってもらいたくないね」
これは原作の部分。ニコ動の画面を流れるような、突っ込みを自分に入れている。どれだけ現代の、今の、日本的なんだろうか。
そう前川知大は、地下室からニコ動らしきサイトでいるかいないか分からない相手に向かって、語りかけるという設定
で、「地下室の手記」をはじめる。かなり置き換えをしているかのような印象を与えるが、実は、かなり原作にはかなり忠実だ。「地下室の手記」の二章がほぼ丸ごと使われている。一章は哲学的や思想的、自分の身上が書かれていて、それは上手に今に変えられている。
今の現実感から、場面ごとにぐいぐいと虚構世界に入っていくという、前川知大の真骨頂はここでも活きていて、いつのまにかドストエフスキーの世界に入り込まされているのだが、それとは気づかせない。凄いな。このテクニックは。
この違和感のなさは、どこからくるのだろう。
前川知大が以前に読んだとき、自分のことではないかと思ったと、書いているくらいだから、元々、自分のものになっているのだろうが、こういう自己愛の男、今ならどこにでもいるよな。自己愛の強い落ちこぼれ官吏は、おそらく何パーセントかは、帝政ロシアの時代と社会が生み出したのだろうから、それを思うと、今の日本は、あの時代と同じくらい人を暗くする、圧迫感があるのかもしれない。
それにしても、たくさんいるよな。こういう男。
update2013/08/22