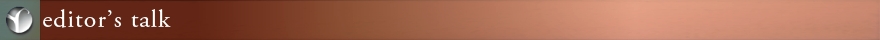stages
第二の秋 シュルツ 勅使川原三郎
第二の秋/シュルツ 勅使川原三郎 Ⅰ
父によれば、これは気候のある種の中毒症状であって、その毒は私たちの美術館に所狭しと置かれている爛熟退化したバロック美術に発するのである。
長すぎる秋を苦しめる美しいマラリア熱、多彩な妄想の原因となる。美とは病なのだ____と父は教えた____美は秘密の感染による一種の震えであり、腐敗の暗い予兆である、(シュルツ「第二の秋」工藤幸雄訳)
シュルツの「第二の秋」は頽廃に充ち、さらにぎりぎりの絶望を孕んで、爛熟した果実のようだ。その「第二の秋」を勅使川原三郎が、舞台化した。「春」「ドド」を原作にしたシュルツ・前二作とは、少し演出を変えている。「第二の秋」に入って、かなりその外へ飛翔している。大劇場にふさわしい抜けるような秋の空気感が拡がる。
シアターχで踊ったシュルツ原作の「春」「ドド」を見たときに、思ったのだが、ある種のダンサーや演出家とか、舞台の上に乗る人たちは、小説を読むときに、人物に入り込んで、小説の風景の中を生きるようにして読むのではないかと。もちろん私たちも、主人公に気持ちを投影して読むというのはあるが、さらに主人公になって、小説の中であたりを見回したり、もしここで風が吹いてきたら、こんな風に感じたり動くだろうなというようなことまで分かってしまうような、読み方。
勅使川原三郎は、「春」を「春、一夜にして」「ドド」を「ドドと気違いたち」というタイトルに変えたが、一夜にして、気違いたちというところが、作品からでて作品の延長として、描いたところだと思う。両作品とも、短編が朗読され、その朗読を音楽として踊っていく。踊りと合わせて聞いていると、勅使川原三郎がどうシュルツを読んでいるのか、そしてどうそこから出てイマジネーションを拡げているのか、リアルに伝わってくる。
この2作品で勅使川原三郎の、これからの覚悟が伝わってくる。どう踊るのか、どうそこに居るのか/あるのかということをより優先使用としている。大きな劇場公演では、見せる要素、ドラマッティックに盛り上げる要素が、踊るということに付加される。勅使川原三郎は、視覚的演出にも特異な才能をもっている。(どこかで歪んだパースペクティブとか……)それを極力抑えて、踊るということに、晒しても踊るということに特化していたのが、シアターχでの2作だった。
一転して、東京芸術劇場での「第二の秋」は、作品から出て自由に踊る部分が多く、演出も従来のようなエッジのたった、光を駆使した演出も入った舞台だった。大劇場は、このままに世界に招聘される演出と躍りで続けていくのだろうが、おそらく、自ら作った劇場と小規模な劇場では、踊る身体を変容させながら変化を続けていく踊りを選んだのではないだろうか。
update2013/09/16