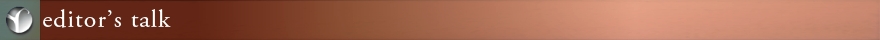『未完のカフカ』 山本直彰

未完のカフカ。
山本直彰はカフカになった。
たった一枚の絵を依頼したのに,山本直彰は、100号10枚の絵を仕上げて連絡をよこした。何か言え。山本はそう言った。それは、長いこと芸術に関係してきた自分に、本気で相手をしろ言っているようにも聞こえた。
これで充分だけど、むしろ充分でない絵を描くことが今の時代の枠を壊すことにならないか。その可能性が絵から伝わってくる。もっと壊れたがっているように見える。と答えた。
山本は最後の2枚の絵に、それぞれ白い本のような扉と黒い扉を描き潰して、そこから次のシリーズが描き始めた。また何10枚かの絵ができ上がり、それは次第に白いトーンになっていき、文学的に言えば余白に描いているような、隙間の空いている、絵画の構成から外れたような、それでいて集約感のある作品になっていた。その昼光では真っ白に見える絵ができ上がって、夜想の締め切りがきた。50枚近い大きな絵が夜想に用意された。2014年、2月、3月の2カ月のできごとだった。
編集に時間がかかり、出版と展覧会が10月に決まり、そこからまた展覧会用に山本直彰は、カフカ描きを再開した。特装本に収めるドローイングを含め、展覧会には100枚の描き下ろしが用意された。そして、山本直彰は、完成を求めず「かく」カフカになった。
『カフカの読みかた』
展覧会のタイトル『未完のカフカ』にはいくつかの意味が込められている。ブロートが仮に(そんなことはないだろうが)カフカの指示通り原稿や日記や手紙を消去したとしたら、カフカは完結した小説を数点発表した作家として歴史に刻まれることになる。ブロートがブロートのやり方で、カフカの原稿を小説にしたために、カフカは、未完の作品を多く書いた作家として世界に流布していった。しかもブロートが手を下したために作家像も作品も実際のカフカとは異なったものとなった。
ブロートの手から逃れカフカの実際に近づこうと批評版が出され、さらにノートを写真で記録した史的批評版が出され実像は次第に明らかになろうとしている。しかし長い間、ブロート/カフカのカフカが流布していたのだから、イメージの払拭は簡単ではない。未完の作品をどう読んだら良いかということは簡単ではないからだ。それは順番の決まっていない16冊のノートの束になっていたりするからだ。カフカの未完作品は結果として近代小説に何ものかを突き付けることになっている。
ブロートのカフカとかなり異なる、そしてカフカの行為にかなり近い史的批評版を読まなければ、カフカについての作品が作れない、あるいは語れないというのが、作家や批評家の気分だろう。日本語訳は見込まれないから、わたしたちはカフカの前ですくんだ状態になってしまう。
立ちすくまず未完状態のカフカ作品に向かい読書するには、従来のカフカイメージを掻き分けて、「未完」を開放することが必要かもしれない。更な状態で未完のカフカが発表されたわけではないから、どうしても従来のカフカ、従来の物語読みから逃れるのは難しい。夜想の『カフカの読みかた』は、作家の得意とする方法、ピアノを弾く指、絵を描く手、演劇をする体…そんな身体を通してカフカを読むという行為を見せてもらうことで、カフカの未完状態に近づく読書法を模索する提案である。
『未完のカフカ』
プラハに留学した記憶を現代に甦らせつつ現代の視点でカフカを改めて読み、カフカをテーマに100枚を描いた山本直彰は、ある種カフカであり、カフカの「未完」状態に、そして今、表現としてカフカの未完は有効な形式なのではないかということも含め、身をもって迫った。それがパラボリカ・ビスの山本直彰『未完のカフカ』である。未完のカフカに近づいたというよりは、カフカになった山本直彰が、カフカの『未完』を開放したと感じた。それで展覧会のタイトルに『未完のカフカ』とつけた。未完状態で書きつづけたカフカの何かをこの展覧会は見せてくれている。それは山本直彰が意図したことではなく、カフカに取り憑かれたように描いた結果としてである。それでこその『未完のカフカ』なのだ。
update2014/10/15