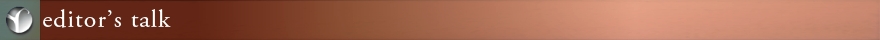stages
開幕驚奇復讐譚 曲亭馬琴
菊之助宙に舞う。
猿之助の十八番だった宙乗り。自分で宙に乗らなければ宙吊りになってしまうと、空中での演技を語っていた。国立劇場の『開幕驚奇復讐譚』で、菊之助は空中での演技を踏まえ、さらりと宙乗りをこなしていた。
そうか宙乗りはもう澤瀉だけのものではないんだな…。時代というのは恐ろしいものだ。芸を継承していないと嘆かれているが、どこかできちんと受け止められて進化している。停滞しているこの状況の中で、少しでも過去を踏まえてのびていくものを見るのは、ある種の救いにもなる。
国立劇場の復活芝居は、澤瀉の専売特許だった。そして一方、小芝居系の復活ものは、澤村宗十郎や加賀屋歌江が引き受けていた。興行しやすい演目を選んでいく松竹歌舞伎によってかえりみられない出し物が多くなっていくことに対して、国立劇場の歌舞伎は大きな役割を果たしてきた。成田屋の歌舞伎十八番にしても、『象引』をはじめとして二代目松緑が、国立劇場で復活させたからきちんと十八番揃っているということもある。宗十郎が亡くなって、猿之助の活動が停止して、復活もこれまでかなと思っていたら、菊五郎劇団が引き受けて継続している。
菊五郎劇団の復活で印象的なのは『小町村芝居正月』で、菊之助の狐が絶品だった。菊五郎劇団の成功は、古風な味を出しながら現代性も持つという、ところで菊之助がその古風さを担当しているのがここの面白いところだ。
『開幕驚奇復讐譚』での宙乗りは、両花道の上に、菊五郎、菊之助がそれぞれ宙に舞う『両宙乗り』という珍しいスタイルだった。レディ・ガガを若干こなしきれずに終わった、菊五郎の不完全燃焼が利いたのか、上花道の上の菊五郎は白犬にまたがってちょっと手持ちぶさたのように見えた。(実際は難しいし余裕はなかったかもしれないが…)両宙乗りは、両花道演技の延長だが、この部分はちょっとまだこなし切れていない感じだった。
もともと左右花道に役者が乗ったら、演技はそれぞれということになる。片方で演技していると
きは、片方がとまっているという歌舞伎独特の作法が、ここで生きてくる訳だが、それが見上げる中空の両花道になるとどっちを見て良いか分らなくなる。先に菊五郎にたっぷり演じさせ、その後、菊之助…かなとも思うが、それはおそらくベストの解決策ではないだろう。言えば味方同士というところも難しかったと想像する。
菊五郎劇団は立廻りの技術も要員もたくさん抱えているし、そのあたりをさらに生かすようなこうした復活ものは実に歓迎すべきところだ。世話物や團菊祭での力量発揮以上に、こうした古風さもあり、立廻りもあり、ケレンもあり、そして世話物的な庶民的な情もある、それがゆえに上演しにくくなった演目をもっともっと復活して、松竹はそれを本歌舞伎に取り入れて欲しいものだ。
update2011/11/01
stages
ドグラマグラ 夢野久作 飴屋法水 吉田アミ 大谷能生
朗読デュオのための『ドグラ・マグラ』/夢野久作 読み
なんど読んでも面白い『ドグラ・マグラ』だけれど、大谷能生と吉田アミの朗読デュオで使うので、少し違う視点から読んでみました。
二人のデュオに、前回は、笙野頼子の『人の道御三神といろはにブロガーズ』をレジメした。3回、バージョン違いを上演したが、掛け合いのスピードや、即興の度合いによって聞こえてくるもの、見えてくるものが異っていて、それは、読むたびに印象が変わる読書のようだった。大谷能生が本読みだということもあって、女性要素のある神を、日本史の中に書きもどすというような笙野頼子の荒技を音に乗せるというパフォーマンスを果敢に挑み、成功していたと思います。声が文学の行間を前に出して来るということもあり得るなと感じます。
『ドグラ・マグラ』のテーマの一つは「私」は如何に存在しているかということです。
私は誰というテーマを、小説の中で、追求していますが、主体の呉一郎が、読者にもそして小説中の「私」にもその人物であるかどうか分らないような形式をしています。まぁそのこと自体とんでもない小説だと言えます。
『ドグラマグラ』挿入されている小説や記述も面白く、特に『胎児の夢』は、様々な人に影響を与えています。一番の記憶は、『胎児の世界』を書いた三木成夫さんで、芸大に会いに行ったときに、屍体の特集号について頼みに行ったのですが、夢野久作の『ドグラマグラ』に出てくる六道絵あるいは九相図のようなものについて書いて下さいと頼んだのですが、いきなり『胎児の夢』と踊る狂少女の話で盛り上がり、三木さんは常に持っているのだと、スーツのポケットから、『ドグラマグラ』の『胎児の夢』の抜き書きを採り出しました。夜想の原稿が気に入らないと、それまでは一切著作物を出さなかった三木成夫さんが『胎児の世界』を著しました。
胎児のうちに進化の過程をすべて体験し、その記憶が残っているというのが、『胎児の夢』の一つの主眼ですが、それは今では、普通のこととして考えられます。もう一つ興味があるのは、考えているのは頭脳ではないという脳髄論(『絶対探偵小説 脳髄は物を考えるところに非ず』)で、これも最近、腸が考えるというような研究が進み、脳の支配を受けずに思考が動くということが実証されています。
夢野久作の作品には、踊る少女が出てくることが良くあります。この不思議な少女と、科学的思考の果てにあるとんでもない、幻想譚。まだまだ三代奇書として君臨する。現代では奇書というよりも小説としてもっともっと受け止められて欲しい。
呉一郎が穴を掘るシーンとか、朗読デュオに使えるシーンはいくらでもでてきます。
http://www.yaso-peyotl.com/archives/2011/09/post_837.html
update2011/09/30
stages
芸術監督というものは
奇ッ怪 其の弐 作・演出 前沢知大 2011/8/27 世田谷パブリックシアター 芸術監督の手腕発見!!
新劇を新劇と感じるもの、歌舞伎を歌舞伎と感じるもの、能を能と感じさせるもの…
演劇にはそうしたジャンルの個性を感じさせるものがある。それは能や歌舞伎の構造とも関係しているが、それだけでは定義できないような感覚だ。長いこと見ているとそういうものがあることに気がつく。
前川知大、作・演出の現代能楽集Ⅵ「奇ッ怪」は、はじまってすぐに、「これは能だ!」と思わせる何かが伝わってきた。舞台はシンプルで、それでいてコンテンポラリーな感じで、ホリゾントをだまし絵のようにして、奥行きがどこまでも深くあるように見せている。現代的な台詞、内容、舞台なのにそこには能がある。
正直言うと、三島由紀夫の近代能楽集に私はずっと新劇の匂いを感じてきた。三島由紀夫の戯曲『癩王のテラス』をこよなく愛してはいるが、そこにはやはり新劇の雰囲気がある。実は、三島の歌舞伎にも歌舞伎よりも新劇を感じてきた。
能は歌舞伎すら引用をするもっとも古い演劇の一つであるが、ずっと能は引用される側だった。ピーターブルックも三島由紀夫も能を引用して自分の表現形式に入れ込んでいる。能の側で新作を作るとUFOが出てくるような、新奇さだけを全面にしたものが多かった。
能の現代劇、現代的に能を創作する…そんな感じだろうか。「奇ッ怪」には能そのものが存在している。形式も感覚も。舞台や衣装や言葉のディテールに古典の能は何もないにも係わらず。芸術監督の野村萬斎が、前川知大に囁くようにディレクションして作り上げた、実験が成功したのだ。
この成功には、野村萬斎の芸術監督としての手腕もあると思う。海外の優れた演劇や演出法を取り入れる、あるいは歌舞伎や能という日本の古典を現代劇に取り入れるという手法に終始していた、ここ何十年かの芸術監督の手法、もっと言えば明治以来続いていた演劇の取り入れ方式に、一石を投じている。
能を能と感じさせるものは、これだよということを上手に前川知大に示唆をしたのが野村萬斎の芸術監督のやり方で、それが本当の意味での芸術監督の役割というものだ。芸術監督はそもそもは、演出家だけがなるものではなく、全体を見れるディレクターがもっともっと腕をふるう場所なのだが、特に日本では、自分流の演出法の延長を、芸術監督の手法やディレクションとしがちである。野村萬斎は演出家で演者であるが、また優れた芸術監督でもあることをこの舞台一つを見てもよく分る。
前川知大も野村萬斎のディレクションを受けて、能を現代的な分析力で構造を見通し、自分が今生きている肉体的感覚にいったん落とし込んでから、脚本を自立させ、そしてまた独自に演出をしている。
野村萬斎の声についての話が面白い。
型とかはもう少し異るダンサーとかと話しをしたらもっと面白かったかも。
藤間勘祖さんとの対話はどうだろう。勘祖さんすごく意識化していると思うが…。
update2011/09/30
stages
深水流 舞踊の会 坂東玉三郎 国立劇場
どめきをとれる踊り手 坂東玉三郎
しばし手踊りをした後、立ち上がる玉三郎に「どめき」が起こった。さもありなん、身体でも壊したかと思うほどにすらりと痩身になっている立ち姿に、ほぅと思わずため息がでる。
低く呻くような言葉にならない響き、そんなほんとうの「どめき」は久しぶりかもしれない。国立劇所の頃…以来? 玉三郎の踊りを面白くて追いかけてきたことがあった。ずいぶんと見てきた。もしモダンのダンサーだったらといつも思った。ちょっと日舞からははみ出していて、それを見るのがこよなく楽しかった。自分の懐に入れて解釈して踊る。そんな意志を感じることが良くあった。
たくさん見た中でもベストに近いかも知れない。いやベストかな。素踊りだったせいもあるが…。歌舞伎役者、素踊りは美しく凄みがある。それは昔、六代目菊五郎と藤間勘祖が、菊五郎に素踊りについて約束事を取り交わしたことがあるということを思い出した。何度か踊りの上手な歌舞伎役者の、浴衣での稽古を見せてもらったことがあるが、それは凄じいというほど素晴らしい。10㎏もある衣装を着ての想定なので、浴衣に身体を叩きつけるように、あるいはいっぱいいっぱいに外に込めて踊っておく。その時の踊りの潜在力というのは、歌舞伎の衣装を着けるとさすがに見えにくい。玉三郎の素踊りの良さは、そうした重い衣装から解放されて、軽く手や身体を振っても綺麗に決まるという逆の感じだった。少し首を振りぎみな、微妙に中心の決まらない感じが歌舞伎の舞台ではあるが、それがまったくぶれず、すっとしている。その軸がまっすぐすらっとしているところから、オーラがダイレクトに客席に向って放たれている感じがして、深く、深く見入ってしまった。
「どめき」が起きたのは、遊女が山姥になった瞬間を受け止めたからなのかもしれない。それにしてもとんでもないものを見せてもらった。
update2011/09/15
stages
十二夜 串田和美演出 シアターコクーン
役者が巧いとか下手だとか
役者が巧いとか下手だとか、感じさせること自体、演出家の責任なんだろうな……とふと思う。
00年代の演劇や飴屋法水の演劇を見ていると、そういうことは感じない。役者というのはまず一生懸命に、巧く演じようとするから、まずそこを止めて、演劇そのものに集中してもらわないとね。
シェークスピアのしかもよく知られている十二夜を演出するのに、フェリーニの映画風に演出してみました、自由劇場みたいに役者が演奏してみました、役者は自由に『十二夜』を思ってください。そうしたらいろいろな面が出てきます。それを観客も自由に楽しんでください……というような演出は、今の時代にいかがなものか。
というか駄目だなぁ。
役者は戯曲を解釈して、それでこれまでの演出と串田がどうちがう演出をするのかを見極めて、それで自分としてはどうそこに対するのかを決めて、稽古でバトルする。その過程を含めて演じるのがシェークスピアだと思う。
オーケストラで演奏するものを即興のフリージャズ風にやってみましょう……というのは意味がない。やるなら新作でやれば良いのだと思う。指揮者がどう解釈して、それをオケがどう受け止めるか、そしてどこで統一感を見いだすのか、あるいは少々、ずれたままでやるのか……再演という行為は、解釈のおもしろさ、さらに言えば、それが今の感覚にどこでつながれるかを見いだす、永遠のトライである。
何十年か前ならともかく、ちょっとこんな風にしました的な演出はまずいなぁ。しかも誰もがフェリーニの映画を思い浮かべてしまうようなコピーの映像的手法は……駄目ですよ。音楽もそれだけでシーンを表現できるほどのものが良いし、映像も台詞を越える何かを伝えるためなら面白いと思う。
ラストの一人二役を、台詞だけで棒立ちで演じさせるのは、松たか子にちょっと酷じゃないかなぁ……。役者がよぉーっしっと燃えるようなハードルなら良いけれど、これじゃぁ困っているのが見え見えだ。
コクーン歌舞伎でも演出を手に入れるのに、だいぶ時間がかかったけれど、今の時代、最初からばしっと見せないと次はないからねぇ。
update2011/01/12
stages
表に出ろい! 野田マップ番外公演
野田秀樹役者として巧すぎる。勘三郎のアドリブ嵐を受け止めて、返しているじゃないか。
変えてしているだけじゃなくて、一撃を加えたりもしている。
歌舞伎座の勘三郎公演に、役者としてでる。というのはどうだろう。台本も野田秀樹で。
で、演出は、うーん。思い切って蜷川幸雄とか。
歌舞伎に『お江戸みやげ』という演目がある。江戸に行商にきた二人のおばさんが、役者に入れあげて、でもその役者は自分の駆け落ちのためにおばさんを利用して……というもの。二人のおばさんを演じるのは宗十郎と芝翫だった。川口松太郎の脚本で喜劇で人情噺。騙されたと知っても良い夢を見させてもらったよと許すというラストの件が客をほろっとさせる。
『お江戸みやげ』書き物で、限りなく普通の芝居に近い。歌舞伎の役者が歌舞伎の枷からの逃れるとこんなに巧いものなのかと舌をまいた。宗十郎さんは俳優祭でも天才的なトリックスター的演技を見せる。珍しく喜劇ができる歌舞伎俳優だ。で、宗十郎さんは分るとして、あの真面目な芝翫さんまでが、宗十郎さんに遅れをとることなく、その真面目な演技のままに客を笑わせたり、泣かせたりする。歌舞伎というのはほんとうにとんでもない芝居だなとつくづく思う。
役者の喜劇力、客を笑わせるやりとりに驚いたのは、それ以来だろうか。確かに新感線も古田新を筆頭に笑わせることには一芸ある。それでも新感線は役者と台本と演出との絡んだ演劇の仕組みを使って笑わせているのだ。ここのやりとりで客が笑わなかったら、それをネタにして、ほら野田さん、演劇やったらドン引きになるって言ったじゃない、だから嫌だっていったんだよ…なんて切り返しでそのこと自体を笑いにしてしまう。役者同士の呼吸と間合いで役者の地力に驚いたのはそれ以来だ。
勘三郎がうまいのは分っているが、野田秀樹の役者っぷりも巧い。夢の遊眠社のときよりも役者として巧い。夢の遊眠社の役者の巧さは当然で、かれの身体感覚が拡大されたものが劇団だったからだ。(今の野田マップも少しその傾向がある。それは演出としては余り好きじゃない)勘三郎とのガチの役者バトルで、一歩も引かない、引かないだけじゃなくて勘三郎をたじたじさせたりする。凄いな、という位の役者力量だ。笑わせるという演技ではなく、二人が舞台で真剣に馬鹿なことを演じているのを、見たら面白いでしょうというやり方である。その真剣度合、馬鹿になり度合いを、舞台の上でやりとりしている。
野田秀樹の世代は、少年性に対する執着が合って、いつまでも若者の感覚を持っている、あるいは分る人でいようとする。若い子が使う言葉や、感覚を演劇に描き込む。10年ほど前に書いた野田の『農業少女』ではとどいていなかった若者感覚に、『表に出ろい!』は、だいぶ肉薄しているの。でも能書きを垂れるところが少し合って、それがなければなぁと思うところもあるのだけれど、それだと野田演劇にはならなくなってしまうんだろうなとも思う。
日本の演劇が芝居からなかなか脱却できないのは、おそらく野田秀樹や中村勘三郎がとてつもなく役者であるからで、究極それで成立してしまいそうに思えるからだ。システムで集団表現するのが不得意な…F1だってオーケストラだって…国は、おそらく世界的という支点の中ではアジアの中でも一気に置き去られてしまうんだろうな。あ、そうそう現代美術もね。
update2010/09/13
stages
2人の夫とわたしの事情 シスカンパニー
笑いの演出が……
上手で感心した。
シェークスピアには道化が出てくるけれど、舞台でこれほど笑えないものはない。どこがおかしいのかが古すぎて分らない。無理に現代の言葉で洒落にしたり、いろいろ演出や翻訳が工夫するけど、結局は、そこは笑いの場面ねと思いつつパスする。
古典の笑いはほんとに難しい。歌舞伎にも道化的なものがあるが、上手だったのは澤村宗十郎さん。国立劇場の復活芝居でも面白い笑いを見せてくれた。俳優祭でも菊五郎さんの笑いじゃなくて、芝居のくすぐりをもっていた人だ。
サマセット・モームの古典劇で笑わせる、しかもかなり現代的な感覚も入っていて、それは言葉尻だけじゃなくて、生活感的、なう
というような感じかな。とにかく笑いの場面で感覚が保留されてしまう古典劇の演出とはまったく違うものだった。
巧い、凄いという印象だ。笑いの演出、どんな風にしているのだろう。自分も笑いが得意じゃないので、演出の方法がちょっと想像できない。
ケラリーノ・サンドロヴィッチの演出は、他の部分も実に本格で、もしかしたら今の段階で、古典劇を演出するコンテストがあったら、野田秀樹や蜷川幸雄よりも上手だと思う。いわゆる劇的な手法……60年代、70年代にはやっ演出。野田秀樹も、蜷川幸雄もまだその延長にあると思うけど、ケラリーノ・サンドロヴィチはその流れにはない。その後世代なんだと思う。商業演劇(古いなこの言葉も)でもっと評価されてもいいんじゃないかと思う。花もあるし。松たか子、段田安則、渡辺徹が生き生きと見えたもの。
パンフレットのなかで、僕には野田さんの言葉は演出できないですよ、野田さんが影響を受けた唐十郎さん、寺山修司さんの戯曲もできないと言っていたが、為たり、と思う。今性を取り入れた人たちだけど、それを戯曲で固定したままではできないということ。演出と戯曲がいったいとなっていたものを他の演出家ができないということ。それが言いたいことだと思うけど、すらっと言っていて演劇人としたかっこよいな。
野田秀樹の「農業少女」の戯曲に表れる今は、オジサン臭くて古い。それはオジサンでちょっと今からずれているのをネタにしているさんまと似ていて、本当にずれてしまっているのをネタにする他ないことの悲哀だ。高いところにいるとやっぱり地面が見えなくなるのだ。
老いてきて今がとらえられなくなるとき、そんなに無理をしないで老人の芝居をすれば良いのにと思いけれど、当事者はそうはいかないんだろうな。
ケラリーノ・サンドロヴィッチは今たくさん見てみたい演出家だ。
くどかんや、まつおが笑いのクリエーターになっているが、ケラリーノの本格もなかなかあなどれない。
笑いながら感心してしまうからね。
update2010/04/23