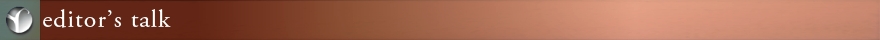stages
花組芝居の牡丹燈籠

さほど空席が目立つわけではなかったが、「お客さんを呼んでください。しゃれではなくやばいんです。」と渡辺えり子は終演後の舞台で客席に呼びかけていた。
1997年10月の紀伊國屋サザンシアターの『ガーデン』を最後に渡辺えり子の劇団3〇〇は解散した。
劇団3〇〇の前2作の『夜よさよなら』『深夜特急』も良い作品だった。感心するほどの。
良いものを作ると客に見放されるというのは、どうも良くあることで
満員でない花組芝居の『牡丹燈籠』の出来がとても良いだけに少し心配になった。案の定、終演後に花組芝居の加納幸和が独り舞台でお客さんをと訴えていた。まさか経営が悪くなることもないだろうが、心配は心配だ。
花組芝居の創立は1987年だから活動はもう20年にもなる。今回の『怪談・牡丹燈籠』の主役・飯島平左衛門を務める水下きよしは50歳を越えたと自ら宣言している。こっちももう20年通っているのか…。
若手も育っている。劇団主で脚本、演出をしながら舞台にも立つ加納幸和のお峰の相手をした伴蔵の小林大介、小悪党を演じてなかなか上手だ。
花組芝居の『怪談・牡丹燈籠』は、歌舞伎で使っている黙阿弥の台本でも新劇で使う大西信行の戯曲でもなく、その元になっている三遊亭円朝のものだ。円朝の原作本は落語で演じ続けたものを速記で起し構成をしたもので、完成度の高い文学にまで仕上がっている。当時、書けなくなった二葉亭四迷が参考にしたことから、明治文学の根元とすら言われている。
加納幸和は、幽霊の話と仇討ちの話が入子になっている円朝の本を見事に芝居にしたてている。加納幸和の戯曲や物語を読み込む力にはいつも感心させられる。鏡花の『婦系図』の読み込みなど、思わず唸るほどのものだ。あ、物語はこうなっているのか、と良く分る。鏡花の読み込みは、当代一かもしれない。この本を読む力が今回も遺憾なく発揮されている。円朝の本の根底に流れている近代性と古典性を明確に描いている。
三遊亭円朝は、何だか僕の中でもブームで、ここ2月ほど、落語を聞いたり、本を読んだりしていた。花組芝居も円朝かとちょっと吃驚した。あちこちで円朝を見かける。だから流行に乗っているんだと思うが、少し観客席が寂しい。
劇団のプロフィールにもある、『高尚になり、堅苦しく難解なイメージになってしまった『歌舞伎』を、 昔のように誰にも気軽に楽しめる最高の娯楽にする』という部分がも失われてきているかもしれないと。本家の歌舞伎よりも深く考察された脚本と演出は、観客の考える行為を必要とする。演劇としてレベルの高いことが観客数に必ずしも反映しないこの国の事情に負けないで、素晴らしい舞台をどんどん作り出して欲しいと思う。
頑張れ花組芝居。で、みんな見に行って欲しいな。
update2008/09/16
stages
劇団ペニノ 星影Jr.

有効な分析言語をもっているのは
精神科医かもしれない。
サンデー・プロジェクトで最も有効言語を放っていたのは
香山リカ、東浩紀だった。東浩紀は哲学だからそれには当たらないが、手法が人の精神を分析することを含んでいる。
+
少し前にみたイプセンの『野鴨』を演出したタニノクロウが、自分の劇団で『星影Jr.』を上演するので、見に行った。いろいろ思ったけれど、一番感じたのは、演劇の習慣的な枠をかなり壊そうとしているということだ。
まず言葉に関しては…歌舞伎、新派、新劇、小劇場…それぞれに独特な台詞回しがあって、それはもちろん日常生活で使われない言葉だ。そのインとレーションが、ジャンルを分けているといっても過言ではない。つまり特色をもたせているということだ。
どんなにリアルな演出といっても舞台の上の言葉は、演劇という枠に囚われたイントネーションをもっている。だが、庭劇団ペニノの舞台で使われる言葉は、かなり現実生活の会話の調子に近い。しかも役者同士が話している言葉だ。演劇の言葉は、対話をしているようで実際には観客に向けて放たれている。演出家・タニノクロウはそうした習慣となって硬直化している言葉を組み換えて解き放とうとしている。
ただし「かなり」というところがみそで、完全に日常ではない。演劇なんだからそれはあたりまえなんだけど、ふと日常か?と思わせるところがある。その「かなり」の部分がタニノクロウの新しい演劇感覚なのだ。
++
『星影Jr.』は、主役で子役のラヴェルヌ拓海が、2年前にフランスから日本に来て適応勉強中で、その彼のために役者が「擬似家族」を演じるという設定になっている。観客はそれを開演前に知らされる。これは演劇ですよという枠組みでなく、これはロールプレイングゲームですよという枠組みを観客に植えつけている。
少年のための教育プログラムとということで、1限目、社会の時間「大人とふれあおう」2限目、家庭科の時間「食べ物を大切にしよう」3限目、体育の時間「心と体を鍛えよう」4限目、道徳の時間「自由な心を持とう」という具合に進んでいく。疑似家族ゲームは、非常にリアルなやり取りから次第に、いわゆる不条理なできごとになっていく。
ウィンナーという妖精(?)の様な小人が登場したり、屋根裏に隠れ棲む婆が現れて盗み食いしたり、妻が犬になり、愛人突然現れて母の代わりをしたりする。妄想や夢の中では思ったり言ったりしたことが、そのまま現実になるということなのだろうか。そして突然、演劇は終焉する。
物事や演劇には整合性があって、結末があったり物語的なまとめがあるという安心感に対して、タニノクロウはかなり強烈な楔を打ち込んでいのかもしれない。『星影Jr.』からは、現実はもうそうした整合性をもっていませんよ、それに気づかないふりをしているんでしょう、という彼の現実的なメッセージを強く感じ取ることができる。
最後は、全員がでてきて葬式の風であるから、誕生日の前に少年が死んで、その少年が見た妄想が描かれたという枠に入っているのかもしれない。もしそうだとしたらその部分は、普通の演劇の枠だ。それが微かにあるだけで、劇団ペニノはかなり従来の演劇のルールから逸脱している。
+++
舞台装置にも革新性が見て取れる。庭劇団ペニノは、客席を個室状態にしてイヤホンで音声を聞かせたり、野外テントに廃墟空間を作ったりして、舞台装置にこだわりがあるのだが、今回は、昭和初期を思わせる家をかなりリアルに作っている。「かなり」りあるというその「かなり」にタニノクロウがいる。
かなりリアルなのだが、どこかに箱庭的な不思議なミニチュア感がある。その集約的な感覚に、現役の精神科医でもあるタニノクロウ独特の現実感が反映している。病んでいるという言い方ではもう済まないほどの病みは、そこを常態として受け入れないと過ごしていけないだろう。それが病みと同棲する唯一の方法なのかもしれない。タニノクロウの世界に、近代的自己や自我はでてこないのだ。そこには、理由もなしにずれていく人と人の関係がある。
update2008/08/18
stages
キャラ立ちⅡ 福助

もしかしたら歌右衛門になるかもしれない
福助だが…
本領は他にあるかも。
八月納涼歌舞伎。野田版『愛蛇姫』。オペラ・アイーダの翻案。
それは良いのだが、どうにも野田シナリオぱっとしない。
夢の遊眠社時代に文語調の高速長台詞で煙に巻きながら、筋を絡めていくという相変わらずの手法を
歌舞伎座でも披露しているのだが、
勘三郎そこにかかると台詞が突っかかってしまう。そりゃぁそうだ。意味が分り難いもの。
おまけにだじゃれのオンパレード。昔は言語遊戯だった言葉の切れも今やだじゃれになってしまっている、野田秀樹。
収穫は福助。
扇雀の偽祈祷師・荏原( えばら)と福助の偽祈祷師・細毛(ほそげ)。
江原と細木なんだけど、キャラを作ってなり切っている福助の演技が面白いし巧い。
扇雀、福助ともに俳優祭で生き生きとしているタイプの役者だけれど
扇雀は扇雀の演技でコメディ。福助は福助がいなくなってキャラになって面白い。
福助は圧倒的に今どきだ。
新感線の『五右衛門ロック』の森山未来のキャラ立ちにも書いたが
役者の自分を消してなるというのは
ほんとうに面白い。
update2008/08/16
stages
歌舞伎座の快楽

歌舞伎座の快楽は
お茶とお菓子。
お茶は揉みだしの200円。あったか緑茶。
お菓子は杏大福。
良く買い占めらてしまうので、歌舞伎座に入ったら速攻、二階に走る。
お茶を飲み終わって
からのお茶をもって次のを買ったら
あ、お湯さしましたのに…
と言われた。
サービスで二杯目にお湯をさしてくれるらしい。
歌舞伎はともだち
で、裏技はかなり取材したつもりだったが
20年の不覚。
そうなんだ…ちょっと、とっても嬉しいかも。
update2008/08/14
stages
『五右衛門ロック』 新感線
80年結成の新感線。
今だにやんちゃなパワープレイをする新感線。頭が下がる。さすがに古田新太のパワーは落ちぎみだけど…。もともとバイ・プレイヤーなので主役をすると照れが出るのかもしれない。
群舞の役者たちのジャンプの高さにちょっと驚く。そんなにパワーを出さなくてもコマ劇場なら効果で充分見せられそうなんだけど…原田保の照明もメタルの生演奏もパワフルなんだから。
いや、そうじゃない。役者で見せるんだ。役者のパワーで見せるんだという新感線の意気込みがいいなぁ。普通、四半世紀以上やっていたらやっぱりテクニックでかわそうとするだろうに。
ベテランになった時、どうするか?
これは大きな問題だ。
野茂英雄はコントロールを良くするためにフォームを変えた。
村田兆治は今だにまさかり投法でシニアで活躍している。56歳で140キロ。でも大リーグの始球式では緊張して120キロ。このあたりにも考えることがたくさんある。野茂は大リーグで投げ続けようとした上での決断だから…。
歌舞伎は、歌と舞いと演技でできている。現代の歌舞伎を標榜する新感線も、同じように歌(メタル・ロック)、ダンス、演技という三つの要素を軸に舞台を作っている。ゼロから物語を作りはじめ、曲を作り、踊りの振りを作る。舞台では、バンドが生演奏をし、登場人物がそれぞれ場面ので歌い、ダンスを踊り、演技をする。それぞれの要素すべてをオリジナルで作り上げ、コマ劇場のような大きな舞台で見ごたえあるものに仕上げるのは、とてつもないエネルギーと創造力とスタッフ力が必要だ。新感線はその実力を備えている日本でも珍しい劇団だと言える。
新感線は、上演の度に新しい試みをする。
今回は、出演者の全員がストレートな主役的な演技をするという挑戦をしている。いつもなら肩透かしのようなギャグを連発して観客の期待の裏切りながら物語を進めて行くのだが、今回はそれぞれの役者がカッコ良い演技をしている。現代ではカッコ良く見える演技はなかなか難しい。演じる自分も恥ずかしいから。
そこに恥ずかしがらない北大路欣也をゲストに入れた。古田新太、橋本じゅん、 高田聖子たちの劇団員も珍しくストレートプレイ。敢えて役者の力を真っすぐにぶつけ合わせた演出は、もちろん大成功している。特に森山未来の演技がきらきらと輝いていた。森山未来は、きっと肩透かし的な演技をしたがる役者だと思う。たとえば松田優作の斜に構えたスタイル…。しかし、いまは、ストレートな演技を磨くとよいと思う。今回の演技のように。
森山未来はダンスの感覚があって、なおかつどこかに変態チックな身体感覚がある。身体的な特質を全面的に出して、カッコ良さを追求したら大きくブレイクすると思う。(たぶん世の中的にはもうブレイクしているのだろうが…)
市川染五郎もゲスト出演した時、生き生きとしていた。今、新感線は役者をブレイクさせる力を持っている。かつて蜷川幸雄がもっていたような力を…。
update2008/07/21
stages
『Root Beers』 KAKUTA

いつもは女子目線で描く桑原裕子が
男目線で描いた『Root Beers』。
アメリカのコリアンタウンのモーテルに、アメリカまで人殺しに遠征して来たヤクザたちのグループがたむろしている。でも様子が少しおかしい。ヤクザの親分が車にはねられ、ルート・ビアを飲んでひっくり返ってしまったからだ。心配そうにベッドの親分を見る子分たち。部屋にはその他にヤクザたちに監禁されている二人の男たちもいる。一人は親分を引いた男、もう一人は親分を売ろうとした情報屋。物語はそんな始まり方をする。
目が覚めると親分は記憶を失っていた。そして人格が良い人に変わっていた。親分は、記憶を失ったことを子分たちに気づかれないようにしならながら、監禁している男たちと話しをする。少しずつ自分を取り戻すために。冬子という妹がいて、唯一、心を許しているらしいということが分ってくる。
親分は、つぶやく。「話せる人が一人いて良かった」と。
一人、話せる人がいれば良い。そしたら生きていけるという、この感覚は、逆に、携帯サイトですら相手をしてもらえる人が居ないという感覚の裏返しである。
桑原裕子の書く親分はそれでも死にに行くのだが、それはどこかでこんな僕でもCCで廻ってくるメールが一つあるだけが救いかな…と言って突っ込んでいく彼の台詞と行動に重ね合わせられる。桑原裕子はこの芝居を、2004年に上演しているのだ。情報が氾濫しているなかでの孤独。コミュニケーション不全。何となく分る気もするが、どうしてこんなところにまで来てしまったのだろうか、日本は。
もう一つの視点で面白いのは、女性目線でやって来た桑原裕子が、男目線で書いていることだ。女性の目から見た表現は、これからの主流になるだろう。もちろん現実社会はそんなに簡単に変換はしない。しかし人形でも、小説でも、女性目線のものが多くなった。ふと思うのは、男の欲望表現はどうなるのだろうか? ということだ。欲望とは生き方ということも含めてだ。そこにもし女子性があればそれも含めてだ。誰もが触ろうとしないこの時代の男目線。それを桑原裕子は描いていると思う。
update2008/06/23
stages
『失われた時間を求めて』 阿佐谷スパイダース

『ドラクル』の時の作・演出の長塚圭史は一体、何だったんだ?
海老蔵の我が侭に負けた? それともあれが本来の力?
阿佐ヶ谷スパイダースは、作・演出、そして俳優もつとめる長塚圭史が中心の3人のメンバーで構成された演劇ユニット。その度ごとに役者をプロデュースしてくる。日本の劇団は、どちらかそいうと家族制度のようなところがある。お父さんが作・演出。お母さんが看板女優。喧嘩したら劇団ごと解散になる。他のメンバーはたまったもんじゃない。
『失われた時間を求めて』は、一つのベンチと、それが置かれているどこだか分らない場所、そして不可解な話をし、行動をする人たちの台詞によって成立している。
ずいぶん前にいなくなった猫を探し続ける人、その行動を探って手伝おうとする女性…。猫を探す人の兄弟もでてくる。人を殺したいというネガティブな妄想を抱き続けている男は、落葉を拾ったりばらまいたりナイフを振りかざしたりする。
この演劇は「動物園物語」(エドワード・オルビー作)の設定を使っている。もしかしたら「失われた時を求めて」(マルセル・プースト)のテーマも使われているかもしれない。
設定をパクるというのは、大正時代から現在まで平気で行われているが、いかがなもんか。
それでも『失われた時間を求めて』は面白かった。前衛の匂いすらしなくなった日本で、これは前衛の部類に属する。
記憶と時間と空間というものは、人間の主観によって大きく異るものだ。時代や社会の状況によっても異る。そのずれを描くことで社会格差などを鮮やかに浮かび上がらせるのが、「動物園物語」や「失われた時を求めて」だった。
その設定を現代の日本に置き換えるとどうなのか? というのが長塚圭史の今回の実験ではないだろうか。格差は大きくなり、表の顔と裏の気持は遊離しているにも係わらず、非常に平板に見える姿をしている今の人たち(それは年配者を含めてのこと)が、意識下の最も気になっていることがらによってコミュニケーションするとどうなるか? 実験に答えはない。結末もない。
それでもよいのは、実験の果てに見えてくるものが、かみ合わないままどこにも到達しない関係だからだ。それは、今の現状を見事に反映している。
この演劇を不条理と言うのは簡単だ。でもそうじゃない。不条理にすらなれない、やりきれないさ、だらっとかみ合わないどうしようもなさだ。失われた時間は永遠に失われ、回復の兆しすらない。やり切れなさの向こうにあるのは何だ。
僕の脳裏には白い絶望という言葉が浮かぶ。
update2008/05/18