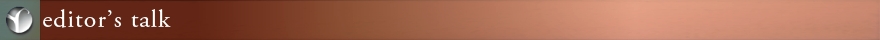stages
『毛皮のマリー』 主演・演出/川村毅 パブリック・シアター
呪縛から逃れる。

この5月4日で、寺山修司が死んで25年になる。
寺山修司が死んで、時が止まっていると言ったら、嘘になるかもしれないが、亡くなられた時のことは、鮮明な感覚として残っている。寺山修司後を生きているという感は今も強い。
今回の『毛皮のマリー』は、森崎偏陸の企画で上演された。
偏陸は、『毛皮のマリー』の初演(1967年)の頃に演劇実験室・天井桟敷に入り、音響や映画の助監督、美術デザインなど、あらゆることで寺山修司の陰で右腕になってきた。「ローラ」という寺山修司の映画では、今でもスクリーンから裸体で飛び出すという役を演じ続けている。
毛皮のマリーを演じるのは第三エロチカの主宰・演出の川村毅で、
第三エロチカはたしか1980年頃の結成だと思うが、俳優としてもユニークな演劇人だった。よく第三エロチカを見ていたのは、新宿アートシアターで、狭い劇場に身体を斜めにして立ったまま(足の位置が床に描いてあってそこに足を乗せて、そのまま終演まで動けない)見ていた。面白かった。
ちなみに新宿アートシアターは飴屋法水の『グランギニョル』が、1984年に「ガラチア」85年に「マーキュロ」を上演していて、これも酸欠になりそうな客席で見て、時代が変わるなと実感した。寺山修司は1983年に死んでいるから、自分にとっても時代にとっても大きなオーバーラップが行われた時だったのだ。1984年はバブル経済の突端であり、ヨーゼフ・ボイスが来日した年でもあった。第三エロチカは「コックサッカーブルー」という代表作を上演している。
川村毅、8年ぶりの主演だということで、しかも寺山修司にオマージュを捧げると公言しているが、演技が古く、かつての新宿アートシアターなら名演なのだろうが、道具もミニマルにしたシアター・トラムの舞台では、ちょっと空回りしている。
僕は、寺山修司に言われた、上演こそすべて、戯曲には寺山修司はいない、という言葉がトラウマのようになっている。寺山修司の演劇は、天井桟敷の上演、寺山修司の演出あってのもので、それが他人の手によっては存在的に意味がないと、寺山修司に信じ込まされてきた。
もちろん演劇において、上演、演出というのは、印象のかなりの部分を占めるという常識は分った上で、やっぱり、ワークショップをやって動きを作りながら台本を書いて、当て書きをしていた寺山修司の戯曲は、寺山修司の一回性の上演ごとに、演劇を成立させてきた、その瞬間だけのものだと思っている。
それとは別に…。ようやく別にというスタンスを少しとれるようになってきた。寺山修司のもっている戯曲の、何かということは見ていきたいと思うようにもなった。それは山口小夜子さんが朗読パフォーマンスをしていたのが、寺山修司の詩であるということに関係している。
寺山修司は、短歌であり、俳句であると思い込んでいたので、詩と向き合うことがなかったのだ。生きた生体としての寺山修司が僕の中に行き続けているので、なかなかそこから逃れられないが、それでも、森崎偏陸や川村毅がトライしたように、戯曲をもう一度読むということは、寺山修司という現象と無関係ではないと、思えるようになるかもしれない。
「毛皮のマリー」は、たしかに女優を気取る男娼の耽美な部分に目が行きがちだが、嘘の母子という関係にこそ寺山らしさがある。寺山修司は、時代の表層を引用して、そこに生成している嘘らしさを、アフォリズムのように晒して見せた作家である。その見方自体に、寺山独特の表現があったのだが、川村毅の演技が空まわったおかげで、台本の構造が良く見えていて、僕には面白い体験だった。
呪縛から逃れることがそれほど良いこととは思わないが呪縛から逃れて見る。そんなことが少しできるようになるかもしれない。
update2008/05/07
stages
野波浩 陶肌曜変


コスタディーヴァには、新に焼かれた恋月姫人形の写真が
マッティナには野波浩の代表的作品群が
納まった。
かなり大規模な写真展になる。会場に合わせ額も焼きも新調された。
update2008/04/11
stages
『追奏曲、砲撃』 桃園会 深津篤史/演出

演劇という形式は、大きくは新しくならないのではないかと思っていたが、そうではないようだ。
桃園会の深津篤史のアフター・トークは面白かった。
ニュアンスとばし
という稽古。いわゆる役者の過剰な張りをなくして、台詞による演劇の原型を
統一のトーンによって静かにアンサンブルしようとする意図があるのだろう。深津篤史には。
指揮者が暴走する演奏者をなだめているような…。
ゴロを捕る名手が試合前に簡単なゴロを投げてもらって何度も捕るような。
ミートの良いバッターが、インパクトポイントのあたりをゆっくり、ゆっくり素振りするような。
タイトルの追奏曲は、カノン。砲撃もカノンから撃たれる。
カノン形式で演出される演劇。
祖母が亡くなって、相続の問題が発生して、敏弘は何十年ぶりかに父に電話をする。父は昔に家出をして今は、沖縄にいて新しい家族がいるらしい。どうも一樹という兄にあたる人もいるらしい。
場面は、黒い大砲の口径のようにも見えるセットを行ったり来たりするたびに、大阪の繁華街と沖縄の海の見える父親の家になるらしい。
見ている限り、それはあくまでも「らしい」であって、「~だ」とは思えない。台詞やシチュエーションがリフレーンして連なっていく。少しも先に進んでいるような感じはしない。
映画「昨年マリエンバートで」が、同じシーンを少しずつ変えて繰り返していくうちに、事実が登場人物にも観客にも分らなくなっていくという表現をしていたのを思いだした。でもマリエンバートのように硬質な感じではない。ふわっとした、何となく間合いがとれない感じだ。
丸いカウンターのような、全体を見ると巨大な大砲の筒口のようなセットを、向こう側に移動して大阪になり、また移動すると沖縄になる。
+
父親との距離、友達との距離、在ったことのない母の距離…そうした距離が実に曖昧なものであるということを、曖昧な感じで表現している。世界は多くの価値観によって成り立っているので、人によって違う世界に見える。だが、個人から見れば偏見だろうが何だろうが、世界は一つに見える。それが少し以前の見え方だった。今は、個人から見える世界も、はっきりとせず揺らいでいる。そんな感覚を作・演出の深津篤史は描いているように思う。
++
いわゆる演劇的な台詞の張りかたをせず、誇張した動きを抑制して、あたかも日常ですらっと出てくるような言葉使いをしながら、その背後に、群衆蠢く社会の中で、膝を抱えているような孤独感を強烈に醸し出している。
+++
こういう演出、描き方もあるんだなぁと、驚いた。

update2008/03/31
stages
『だるまさんがころんだ』 燐光群 再演

台本をいまに書き換えたのかな…あ、全然、書き換えていないんだ。
パンフレットを後で読んで驚いた。
パンフレットには、
今回の上演は、まぎれもなく「今現在の劇」でありながら、初演時である2004年3月という時間、時代をも、確実に舞台上に刻印したいと思います。とある。台本は変えていない。なのに前回見た時よりも、さらに今を感じる。
語り役をしていて、父の無言を描いた小説で賞をとった妹が、突然、通り魔に殺される。一昨日、昨日、今日と、誰でも良かったという殺人が続いて、ここに描かれているものは、何だろうと思ってしまう。問題が起きている地点からは、どんどん問題の芽が放射状に拡がって、別の形になって、そして違う形でまたネガティブに爆発する。
私たちが作るものはプロパガンダではない。演劇である。でもその区分けはどうでもよいことだ。
坂手洋二はそう語る。
+
プロパガンダ、あるいはドキュメントを現実として捕らえる行為、それをそのままに出すだけでも演劇としてしまう方法を坂手はもっている。それはあらかじめ作家の側が妄想した物語によらないということだ。現実によって作るということだ。
++
その上で、演劇として収斂する物語を織り込んで(トッケイという怪物)『だるまさんがころんだ』ができ上がっている。
その織りなしのギリギリ性を保って、何度でも繰りかえせるのは坂手の才能だし、他に見たことがない。
+++
八百長のないゲームは、こちら側の観客や解説者(舞台なら評論家)の想定する物語とまったく相反するところで成立する。突然、終わったり、一方的だったりする。過剰な物語と、解説によって毒されてしまっている感覚から、早く逸脱するべきだ。現実は、あっけなく終わるほど、残酷で魅力的だ。坂手の向っているのは、そんな現実なのだ。
++++
それでも演劇が欲しい。坂手はそれができる数少ない演出家の一人だから。
トッケイは、かちかちと舞台になり続けている、地雷の時限装置の時計の音。その時の象徴。
地球上の地雷の、時計の音は、
今、爆発するしかない巨大な怪物になってしまったよ。
それに対してどうするの?
そういうメッセージが込められているのだろうけど、さらに、坂手に何かを言って欲しかった。
彼くらいしか言えないのだから。
update2008/03/29
stages
filmachine in Berlin report ~進化する第三項音楽/filmachine~

池田亮司さんのコンサートで会った渋谷慶一郎さんの 「filmachine~」のベルリンでのインスタレーションの報告会にアップリンクへ。
会場で三上晴子さんに声を掛けられてびっくり。感じが変わったわねと…。うーん。どこがかな。
+
人間の頭の方に、描きたいものがあって、それを比喩を使って出してくるのがアートだとしたら、音楽の先進は、その人間の頭という部分なしにできないか。例えば、複雑系、カオス系を使って、作曲のシステムを作って、音を空間に発生させる。
++
表現するときに、比喩がなくなる、あるいは最小限になる。
+++
しかし人間のシステムは、そこに人間性、自然性の体系を見いだそうとする。飽きるということもある。アディクションになって快感が発生したりもする。
++++
音を興行的に売りたいという、あるいは売れると嬉しいという欲望のために、綺麗なメロディが発生するようにしたりもする。あっという間に人間性というところに収斂される。だからアートなどと言われたりもする。
この連鎖を断ちきれないかと渋谷慶一郎は考えている。できるかどうかは別にして、今のところそう決意している。
update2008/03/23
stages
『カリフォルニア物語』 吉田秋生 +スタジオ・ライフ
スタジオ・ライフの『カリフォルニア物語』を見に行く。
幕間でイリーコーヒー ちょっと薄い。

吉田秋生の原作は何度読み返しただろう。
僕にとっては自分の住んでいた湘南の匂いを感じる。
理想の男の子像って? 今から15年くらい前に聞かれた時に
吉田秋生に出てくるちょっとワルの主人公かなと言ったら
古ーい。今は、ダメンズと言われたのが懐かしい。
兄弟の父親を挟んだ微妙な嫉妬や愛がテーマ。
ボクにとっては余りに現実的で胸が痛かったり、郷愁をかき立てられたり。
update2008/03/09
stages
『動員挿話』 岸田國士/深津篤史
今、思う限り、岸田國士の戯曲を生かすとはこういうことなのではないだろうか。
岸田國士の昭和初期の短編戯曲『屋上庭園』(1926)と『動員挿話』(1927)が二本同時に上演された。両方合わせても2時間に足らない。
役者は10分のインターバルをおいて、異る2本の芝居をする。これは想像以上に大変な作業だ。しかし役者は見事に二つの役を演じ分けていた。
二本の短い岸田を10分おいて見れるのだから、記憶が鮮明なまま、戯曲を比べて鑑賞することができる。どの部分が岸田独特のものか、どの部分が戯曲の固有性なのか手に取るように分る。男の世間体、プライド、それに対する妻たちの必死さ優しさという構造が、岸田の特色だ。男中心の世界を描きながら、女性の視点も鮮やかに書き込んでいる。岸田にはフェミニズムの姿勢がある。フェミニズムと言うと、女性の側から書くと分かりやすくなるが、岸田はそうはせずに男の側からも社会の側からも総合的に描いている。
ドラマを描くときに、誰の側からという書き方ではなく、登場する人物は社会を構成する人として描いている。だから特に誰が主役という風にならない。敢えて言えばテーマが主役になっている。主役中心でなく、テーマ中心の演劇ということになれば、今なら桃園会の深津篤史だろう。
深津篤史は、後半の『動員挿話』を演出した。
岸田國士の言葉は、推敲を重ね、磨かれて美しい。妻と夫との会話でも文学的な言葉、ときには詩的な言葉すらでてくる。もちろん普通の会話も出てくる。それらの差がほどよく溶け込んでいる。言葉の端々からは岸田國士らしい香りがするし、見終わると演劇はこうありたいという思いや思想が伝わってくる。非常に完成度の高い戯曲である。これもまた深津篤史の戯曲の特色に重ね合わせられる。
+
岸田國士がここまでの演出法をあの時代に体現していたとは思えないが、岸田國士の戯曲の特色を生かして、現代に描くとしたら、今のところ、これはベストと想定できるものではないだろうか。
update2008/02/28