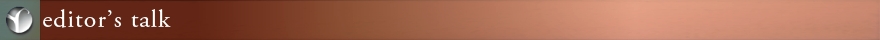books
ドグラマグラ 夢野久作 飴屋法水 吉田アミ 大谷能生
朗読デュオのための『ドグラ・マグラ』/夢野久作 読み
なんど読んでも面白い『ドグラ・マグラ』だけれど、大谷能生と吉田アミの朗読デュオで使うので、少し違う視点から読んでみました。
二人のデュオに、前回は、笙野頼子の『人の道御三神といろはにブロガーズ』をレジメした。3回、バージョン違いを上演したが、掛け合いのスピードや、即興の度合いによって聞こえてくるもの、見えてくるものが異っていて、それは、読むたびに印象が変わる読書のようだった。大谷能生が本読みだということもあって、女性要素のある神を、日本史の中に書きもどすというような笙野頼子の荒技を音に乗せるというパフォーマンスを果敢に挑み、成功していたと思います。声が文学の行間を前に出して来るということもあり得るなと感じます。
『ドグラ・マグラ』のテーマの一つは「私」は如何に存在しているかということです。
私は誰というテーマを、小説の中で、追求していますが、主体の呉一郎が、読者にもそして小説中の「私」にもその人物であるかどうか分らないような形式をしています。まぁそのこと自体とんでもない小説だと言えます。
『ドグラマグラ』挿入されている小説や記述も面白く、特に『胎児の夢』は、様々な人に影響を与えています。一番の記憶は、『胎児の世界』を書いた三木成夫さんで、芸大に会いに行ったときに、屍体の特集号について頼みに行ったのですが、夢野久作の『ドグラマグラ』に出てくる六道絵あるいは九相図のようなものについて書いて下さいと頼んだのですが、いきなり『胎児の夢』と踊る狂少女の話で盛り上がり、三木さんは常に持っているのだと、スーツのポケットから、『ドグラマグラ』の『胎児の夢』の抜き書きを採り出しました。夜想の原稿が気に入らないと、それまでは一切著作物を出さなかった三木成夫さんが『胎児の世界』を著しました。
胎児のうちに進化の過程をすべて体験し、その記憶が残っているというのが、『胎児の夢』の一つの主眼ですが、それは今では、普通のこととして考えられます。もう一つ興味があるのは、考えているのは頭脳ではないという脳髄論(『絶対探偵小説 脳髄は物を考えるところに非ず』)で、これも最近、腸が考えるというような研究が進み、脳の支配を受けずに思考が動くということが実証されています。
夢野久作の作品には、踊る少女が出てくることが良くあります。この不思議な少女と、科学的思考の果てにあるとんでもない、幻想譚。まだまだ三代奇書として君臨する。現代では奇書というよりも小説としてもっともっと受け止められて欲しい。
呉一郎が穴を掘るシーンとか、朗読デュオに使えるシーンはいくらでもでてきます。
http://www.yaso-peyotl.com/archives/2011/09/post_837.html
update2011/09/30
books
まどか☆マギカ
まどか☆マギカに一歩、近づけるのか、近づけないのか。
ふとしたことから、まどか☆マギカにはまっている。
update2011/09/06
books
大山康晴の晩節 河口俊彦
勝ちから見るのではなく、負けから見る。 しかも美しく。
以前、一時、将棋観戦を趣味にしたことがあった。河口俊彦の文章に触れたのが、きっかけだった。たぶん『覇者の一手』だったと思う。TVも観戦するようになり、米長解説で、羽生の対戦を見ていた時に、あ、ここが勝負手ですね。と米長がが呑気な口調で言うと、どっちですか?と司会が聞く。勝負手であることは分るけれど、どっちが有利かは分らない。どこに打てばいいんですかね? それがすぐに分ったら僕は名人になってますよ、盤で対局している人しか最善手が分らないものです。それを聞いて面白いものだと思った。
一分将棋はほとんど格闘技で、瞬間判断になる。それでも盤に坐っている二人にしか見えない筋があるというのは、不思議なゲームだ。逆に側にいて冷静なほうが見えるのは普通なのだが、そうではないのだと興味をもった。負けたすぐ後に観想戦をするのも驚いた。負けた一手を分析して、こうならよかったとまで相手とともに検討するなんて、とても自分に甘い人間にはできない。
勝負に勝ち、名を残すとのは強いということと少し違う。大山にとって将棋はゲームでもプレイでもなく、勝ちという事実を残す人生なのだ。棋譜を残す棋士も居る。谷川などもおそらくそうだ。羽生もその傾向がある。大山はそれ以上に戦績に対する執念があるのだろう。大山は、その姿勢があってA級で最後まで打ち続けたのだ。盤外でも盤内でも使える手はすべて使って勝つ、それが大山だ。河口俊彦は晩年の、もがくようにして盤に向っている大山康晴を、最大限美しく描いている。それは晩節を棋譜から描くという手法をとっているからだ。
癌にかかっていることすら利用するような駆け引き…。話しは少し異るが、WGPの一時代前のチャンピオン、ドゥーハンは、早く走って勝負を決めるのではなく、勝つように走るのが勝つことだと考えていた。引退を決めた後の最終戦、勝つことの呪縛から逃れたドゥーハンは死ぬほど速く、そしてコーナーをオーバースピードで飛び出してリタイヤした。そのすがすがしい顔が忘れられない。早く走れたんだ。凄い!それでも勝てなくなりそうだから引退する、それがドゥーハン。ちなみに250CCで若くして策士だった原田哲哉が、ロッシになんで早さ競争しないんだと、レース中にウイリーして挑発されたことがある。もちろんレースはそれぞれだ。それが人生観なのだから。
F1のチャンピオンの晩節、プロストもセナもシューマッハも、若手を脅したり牽制したりするという、将棋で言えば晩節を汚した。でもそれは汚したと言えるのかどうかというくらい、繰り返されることだ。プロストがセナを牽制し、セナはシューマッハを怒り…。ロッシは今、晩節にさしかかっているが、ドカティに移籍して挑戦をしているように見える。公式発言からは若手を盤外でどうこうしようということは伝わってこない。ロッシの引退までの走りざまがとても興味ある。さらにちなみにもがきつつけたシューマッハが、2011年9月11日のイタリアグランプリで素晴らしい走りを見せた。元チャンピオンとして。ベッテル、バトン、アロンソ、シューマッハ、ハミルトンという歴代チャンピオンが、連なって走り、シューミは、再三のハミルトンの仕掛けをしのぎ続けた。コーナーで二度進路を変更するという違反行為をそう見せないようにギリギリで使い、FIAの勧告が出そうになると、今度はロス・ブラウンが車線を開けろと無線で指示をして、チームはちゃんとやってますよと、そしてシューマッハにもフェアプレイをしろと、チャンピオンらしくと…示した。シューマッハは二つ目の車線変更を緩くし、ハミルトンはそこ隙間をつかってオーバーテイクした。
不必要なブロックを続けることで、晩節を汚しかけていたシューマッハはこのレース、盛りを過ぎた元チャンピオンとして見事なレースをした。復帰してからこのレースをするためにもがき続けていたと言っても過言ではない。でもこのレースができたのは素晴らしい。プロストにはできなかったことだ。
大山は、晩節に美学を求めるような棋士ではない。河口俊彦は洒脱な文章でそのもがきを美しく記述した。シビアに言えば、でもここにも河口俊彦の文学があり、それゆえにこの本は、将棋の分野よりもより文学の方に近いところにある。しかし河口俊彦がこのように大山康晴の晩年を描いたことで、河口俊彦自身が、大山世代とともに自らを終焉に追い込むことになる。河口俊彦に、今の、羽生以降の将棋の面白さ、棋士の面白さを書くことはできない。
将棋を棋士が書く仕事は、河口俊彦から先崎学へリレーされている。それはあちこちで見て取れる。能條純一の「月下の棋士」は河口俊彦が監修だが、「3月のライオン」では、先崎学が監修をしている。先崎学は勝てない棋士、勝たない棋士を描くのに上手なサゼッションをしている。勝つ、強い、戦略がしっかりしているという棋士の優位だけが棋士ではない、その当たりに先崎は目が行っている。河口の視点は、常に優れたものを見いだそうとしている。大したことのない対戦と思われていた棋譜、大したことのない晩年と思われていた大山康晴の晩節を見事にピックアップしている。
これからは勝てなかった棋譜の美学とか、美しく負ける棋士とか、執念の盤組みが崩壊する瞬間とか…勝負の結果、それも勝ちからものを見るのではなく、同じように負けからも棋士の生き様をポジティブに見る筆致が必要になってくるだろう。
update2011/09/01
books
っぽい。 のは避けたい。 っぽい のは嫌だ。『組む。』ミルキィ・イソベ
20代なかごろから40代までずっと踊りの現場にいて、プロなんだからという言葉が出てくる時があるが、それが、究極の危険信号だということに気がついたのはだいぶたってのことだった。プロだからという言葉で押し切る時ほど、危ないことはない。何度か大きな事故を体験して、天井から鏡が墜ちてきたり、火のついたロケットが動かなくなったり、したけれど、本当のプロはプロっていう言葉をはかないで仕事する。はじめた頃の素人の頃の謙虚さをもっている人がプロだ。職人という言葉もそうだ。職人が自ら職人と言う時ほどいかがわしいことはない。押し切る言葉は絶対に何か駄目なものを隠している。余談だけど、政治家のきちんととしっかりも同じような言葉だと思う。何か具体的なものを隠している。
技術は圧倒的に進んで、素人がかなりの技術をあっという間に身につけられるようになった。だけど職人が職人たるゆえんは、その技術の優位性にはない。技術と何かをつなぐところを成立させる、仕上げる技量をもっているところにあるのだ。言うに言われぬ、素人では追いつかないところ。先日、竹本住太夫がドキュメント番組で、義太夫が先に行って待っている、でも義太夫は女房というようなことを言っていた。ディレクターが、相手に合わせるということはしないんですか?と聞いて、住太夫が悪いけどあんたら素人にはわかりまへんとぴしゃりとやっていた。徹底的に大夫に合わせるからこそ、その息を知るからこそ、詰まらないように先に場面があるなどというニュアンスはなかなか言葉にできるものではない。その感じは分らないが、踊りも音を先にやってあとから踊りがついていくという場面があったりするから、そんなことにちょっと近いのかもしれないという位しか近づけないけど、その分らない微妙なうねりのような擦れを作り出すのが、プロで職人だろう。特権とかじゃなくそこでやっているということなんだと思う。
でも普通なら知らないことも、技術や秘密がしだいにオープンになってきて、できないまでも、見えないまでも、分らないまでも、そんなむずかしいニュアンスが、存在するということだけは伝えられる時代になったのではないかと思う。身につけるのは今だなと思う。っぽいというのは、表面が似ていて、そうした分らない、得体のしれないものをもっていないもの、似非のことを言う。技術や情報が進んだ分、似非の精度も上がりなんだかほんものと寸分違わないようなものになってきた。本物の食べ物は、食べ慣れていないと胃が緊張してたくさん食べられなかったり、お腹を壊したりする。やわな似非を食べ続けていると身体がやわになって本物を受けつけなくなってしまうのだ。
『組む。』は、ブックデザイナーのミルキィ・イソベと現場のDTPディレクター紺野慎一が、書いたInDesignの本だ。っぽいのが嫌いな二人とスタッフが作り上げた。っぽいのとそうでない現場魂直球の違いは、説明しづらいが、『組む。』はっぽい要素zeroの本。ミルキィ・イソベは最近、王子製紙のペーパーライブラリーの展示企画もやっているが、まぁ言えば竹尾のっぽさと王子製紙の紙好き本気の差かな。差は、っぽさとそれを排除した侠気のようなものをどう評価し思うかということだけで、別に竹尾をどうこう言っている訳ではない。で、『組む。』の剛毅な本物指向は、本物ということに終わらずに、美しい組版を作るというところに向っていることだ。ここが凄い。なかなか本格とか、本物とかを目指すとその形式で終わってしまうことが多い。この本は、美しい組版を作るという一点に向っている。っぽさの排除とか正しい方法とかは、そのための方法でしかない。
食べ物もそうだけど、蘊蓄なんかより、食べてどう美味しいか、食べて身体が震える快楽にひたれるかしかない。『組む。』も究極は組版の美しさを目指している。美しいものは快楽なのだ。編集者は今やこの快楽の道筋をもっていない。おそらくブックデザイナーがそれを担っていくのだろう。しっかりと、それでいて美しく。ミルキィ・イソベの主張ははっきりと具体的だ。テクニカルな本のように見えて、思い満載の『組む。』。究極の一冊だと思う。
update2010/06/09
books
『陰獣』 江戸川乱歩(1928)
1988年4月8日の未明は、春というのに大雪が降って、開花寸前の桜は雪花を咲かせた。雪明かりに眠れぬまま家を出て、上野公園をさくさくと新雪を踏みながら谷中墓地へ抜けていった。毎年、谷中墓地で桜見をするのに雪は、それも大雪は一度もなかった。雪は音を吸い無音のように感じる公園には、時折、雪の重みで枝の折れる音や雪の木から落ちる音が伝わってくる。
桜は雪に枝垂れて、枝先を重く雪に埋もれさせていた。この異様な風景を覚えているのは、その日、昭和の絵師・竹中英太郎が身罷ったからだ。死亡を知ったのは数日後だったが、絵師に相応しい雪と桜、送り火ならぬ送り花であったことよと感慨深かった。
熱にうなされるように竹中英太郎のことを考え続けた時期があって、それで夜想の特集もできたわけだが、いつもの悪い癖で、英太郎から『新青年』も乱歩も正史も見るという偏った本読みをしていた。改めて乱歩や正史に耽ったのは最近のことかもしれない。竹中英太郎の挿絵を見るために図書館の『新青年』をめくり続けた。英太郎は、たくさんの作家に挿絵を描いたために名を変えたり、名を記述しなかったりして『新青年』に描いていた。それを見抜くのが無上の楽しみでも会った。息子の竹中労氏のように戦後の油絵を本道として英太郎を見る見方もあるが、(そしてそれゆえに竹中労とは最後に袖を分かつことになるのだが…)どうしたって『新青年』時代の挿絵、もっと狭めていえば横溝正史の『鬼火』と江戸川乱歩の『陰獣』を最高作と思うのが当然だ。左翼の人にありがちなエロ・グロに対する軽蔑と、教条的な本格をよしとする芸術観は、そのまま左翼運動の弱さにもつながったと思うが、竹中労の場合は父親コンプレックスと言えるほどの英太郎崇拝によるものだったような気がする。
英太郎は『陰獣』を描いて筆を折り満州へ向う。乱歩は『パノラマ島奇譚』以来の休筆を終えての復帰作であり、二人は『陰獣』で表舞台を交差することになる。『陰獣』と『パノラマ島奇譚』は、どちらも乱歩の力作であり人気作だが、当時の編集長の横溝正史とのやりとりが残されている。乱歩はしばしば正史を責めるように『新青年』がモダンになり過ぎたから僕が追いつめられたのだという。しかし正史は『陰獣』を大絶賛している。『パノラマ島奇譚』に比べ、オドロオドロしき妖気が、粘りっこいトリモチのように、全編にまつわりついている、と褒め、宣伝にも力を入れた。そのかいがあってか、作品が面白かったか、たぶん両方のことで『陰獣』掲載の『新青年』は増刷を繰り返すことになる。
甲府で会わせていただいた英太郎氏も挿絵の仕事を、あんなものは…という風に卑下しておっしゃっていて、息子の竹中労が絵画としての油絵を高く評価しているのを嬉しそうにされていた。横溝正史が、アルコールをやりながら寝る前に、妖しい妄想をするのが日課だったと書いているように、そして英太郎が癩病の少女をスケッチしに帝大の病棟に潜り込んだように、表はモダンにそして内実はどろっとしたものを希求していたのがこの時代の創作だったのかもしれない。もちろんそれは読者の欲望を写してもいたのだろう。
『陰獣』は、クールな語りの探偵と、姿の見えない大江春泥という乱歩そのものの二人が登場するが、書いている乱歩を入れれば三人の私のメタフィクション小説ということになって小説としての面白さがある。春泥は乱歩の作品を解説もするし、覗き趣味的に姿の見えない春泥に乱歩を重ねて読む楽しみもあって、そして創元社文庫だと、英太郎の挿画も当時のままでこの上のないものになっている。
探偵小説の仕組みとしては相変わらずでラストに破綻を起している。小山田静子が大江春泥で、六郎殺しの犯人だという帰結は、女性が化けた春泥のイメージがまったく想起できず、そして前半にもないも布石がないので受け入れがたい。静子が春泥だったと言われて、驚きとともに鮮やかにそうそかもしれない、いや絶対にそうだというどんでん返しでなければ、このような大仕掛けは、逆に、え?ということになってしまう。
一番の破綻は、記者の森田が実際の大江春泥に会っているという設定で、もしそれが嘘なら嘘をつく理由のようなもの書かないと、大きなルール違反だ。森田と静子が組んでいるか、森田が嘘を言っているかのどちらかでないと成立しないが。静子が夫の六郎を窓から突き落として殺すと言うのも、そんなことが簡単にできるかという感じだし、探偵小説家が推理し間違うように鬘を被せたというのも不自然で、それが便器のところに流れ着くというのもちょっと唐突だ。もちろん夫殺しの理由も感覚的に納得いかない。
浅草・山の宿(地名)を中心に東京のあちこちを円を描くように登場させているが、そのあたりは中井英夫のこよなく愛好するところだろう。浅草の外れ、今で言うと裏観音辺りを舞台に大川と堀を絡ませる設定は、人外がうろつく闇の深さを巧くとらえている。ふっと妄想するのだが、春子が春泥になっていたのではなくて、春泥の乱歩が春子になって、女装して鞭打たれたいという妄想の幻想が乱歩の脳裏に渦巻いていたのではないかと。それなら『陰獣』すべてに合点がいく。
update2010/05/28
books
悪魔人形 江戸川乱歩 1970
松丸本舗でお人形を展示するのに
少し、本のリストもお手伝い。
夜想なので、人形と両性具有と…。
人形や耽美やアンドロギュノスの小説を読みなおすと楽しい。
やはり読む動機やシチュエーションで変わるものもある。
本は何分の一かは読者が作るものなのかもしれない。
『悪魔人形』江戸川乱歩 ポプラ文庫
少年向けのシリーズ。これは本人の出筆。
『怪人二十面相』は子供の頃に買ってもらったのがぼろぼろで残っている。他のはもっていないので買いそろえようかな。
中身は変わっていないのだろうか。
中井英夫は乱歩は少年文庫だと言っているが、それも頷ける…ところもある。
少女を美しいまま保存するには人形が一番。などと前半かなり良い感じで進んでいくが
相変わらず後半とっ散らかって、ポケット小僧は反対に向けて走っていったっきり、いなくなってしまうし…最後まで来ると最初のまくらの部分が、あれっ? という不具合。
それでもモチーフで読める一作。
どうせなら探偵小説にしなければよかったのかもしれない。
もともと解決すべき事件ではなく、少女を人形にしたい感覚で押し通せばよかったのだろう。
時代はそれを乱歩に許さなかったのだろうけど…。
両性具有から
双子から
人形へ
読み解いていこうかな。
update2010/03/19
books
『眠り人形』木々高太郎 1935(昭和10)
木々高太郎『眠り人形』が読める大衆文学大系25(講談社)には他に横溝正史、海野十三、小栗虫太郎がおさめられていてしかもそれぞれ名作が選ばれている。選ばれる観点が今と少し違っていてそれがかえって好ましい。よく無人島にもっていくとしたらなどという現実離れした設問があるが、聞かれたら大衆文学大系25。できたら全集をもっていこう。でも本当のところは日本探偵小説全集かもしれないな。
『眠り人形』には、伏せ字が際どいところに連続していて、はてどの位の過激さで想像したら良いのか、××は唇だろうかペニスだろうかと、思いながら読むのも楽しい。ペニス何んて言わないよな。昭和十年なら何というのだろう。創造は楽しいがやはり消化不良になる。伏せ字なしを読むには日本探偵小説全集・木々高太郎(創元推理文庫)がいい。伏せ字が回復したのはそんなに昔のことではない。創元推理文庫の仕事はすばらしい。
『眠り人形』のタイトルから川端康成の『片腕』1963(昭和38)を連想したりするが、『眠り人形』は薬を使って妻を眠りの病気に誘導していって、女性を人形化する。そして…という小説だ。探偵小説には結末へ向って書かれる独特の気配があるが、木々高太郎の小説にそれはない。推理小説と言っているが限りなく純文学だ。伏せ字にされるくらいなので表現も内容も際どい。でもそれが耽美の執拗さに傾倒していて幻想小説にもなっている。川端康成が幻視的な表現でエロティックを押し隠しているとしたら、木々高太郎はエロスで幻想を醸し出していると言える。しかも文学上の設定で書いているのではなく、たぶん木々高太郎は、ネクロフィリーで膚フェチで、尿マニア。真性の倒錯感覚をもっている。しかも中年になってから肉体の愛を知るようになったという件が他の小説に良く出てきていて、少女愛の嚆矢かもしれない。
update2010/03/18