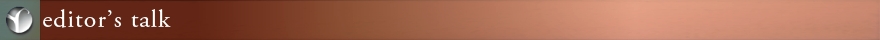books
白蝋変化 横溝正史全集2
『鑞人』
蔵の中で鑞人となった今朝次を愛撫する盲目の芸妓珊瑚。この耽美、デカダンスは類を見ない。
ちょっと話しはそれるが、長谷川時雨は、鏡花の『日本橋』に田舎もので日本橋を知らないと公言した。たしかに日本橋生まれの時雨にとって、鏡花の描く日本橋・花柳界はそぐわないものだったかもしれない。潔癖症だった鏡花が粋な遊びをしたはずもなく、神楽坂の芸妓を妻にしたといっても、それが花柳界というものを体感できたかどうかは分らない。日本橋に出てくる唄でもちょっと気になるところはある。
もちろんそのことと鏡花の文学としての『日本橋』が面白いということは別である。『天守物語』などの荒唐無稽さに現実性が欠けているというのと変わらないからだ。鏡花にしてもなかなか、芸者と旦那の関係をままに描けないものだし、そこに間夫が出てくれば、典型的な物語になってしまいそうだ。歌舞伎にもあるし。が、横溝正史は、旦那が金と嫉妬を振り回す異常さを妙にリアルに描いていて、実際、こんな感覚で旦那は妻にした芸妓と付き合っているんだろうなと思う。そのリアルな感じ、自然主義的な描写を起点に、蝋人形の形代を盲目になった珊瑚が愛するという、不可思議さへ一気に向っていく様が良い。
こね繰り回さない最後もすらっとしていて美的である。
update2008/05/18
books
『ブックデザイン ミルキィ流』 毎日コミュニケーションズ

いま出版制作のシステムが変わって編集者はとまどっている。
みんなはそうではないかもしれないが、少なくとも僕は、そのことでちょっと困ったりしている。DTPをいち早く導入したのに使いこなせていない。そんな編集者たちを相手に、こうしたらいいんじゃないと、ミルキィ・イソベは語りかける。良い本を作ってきたデザイナーの考え方と生き様と気概がこの本に込められている。
本の現場では、アートディレクターの存在が不可欠になっている。そしてそのことでエディトリアル・デザイン、編集、制作が真摯にコラボレーションしないと、良い本ができなくなっている。
ミルキィ・イソベという20年以上、デザイン、編集、制作の現場で、身体をはって考えてきたデザイナーの軌跡は、素晴らしい本作りのノウハウであるとともに、大袈裟ではなく出版への警鐘にもなっている。今、出版は問題を積載したままよたよたと走っている。一方では儲ければいいじゃん、という乱暴な出版もまかり通っている。
そんな現状の中でも、それでも紙が好き、それでも本が好き!! と明るくポジテブな態度で仕事をしていくミルキィ・イソベに、どれだけ編集者たち、著者たちが元気づけられたことか。この本の中には、所謂、ノウハウに近い秘密がたくさん明かされている。明かした目的は一つ。真髄を明かすことによって、好きな紙が残ったり、良い編集者が育ったり、いろいろなことが、何か起きると思ってこの本は書かれている。未来を少し信じている本だ。少しでも未来を本気で信じている本は少ない。それだけでもこの本は価値がある。
良い本と書いたが、良い本というのは存在する。良い編集者も存在する。そしてもちろん良いデザイナーも。価値観あっての出版だ。美味しい食べ物という概念があるのと一緒で、良い本というのは存在するのだ。この本は、そんな本を作ろうとして奮闘してきたデザイナーの、手の証である。
こんなに本の中身のこと、著者のこと、編集者のこと、出版社のこと、読者のことを考えて本を作ってきた人は他にいないだろう。考えていますということを表明しながら、自分のやりたいことしかしないというよくあるあれ、とはまったく異る。本という物理、もの、そして流通してく「ぶつ」としての本の側から見ている。そしてその「ぶつ」に息吹を吹き込んでいく。作家の、編集者の…ときには印刷のディレクターの…。
デザインをするときに「敢えて」中味を読まず、「敢えて」ちょっとミスマッチな感じが良いよねなどというデザイナーはもの凄く多い。結局、いつもの自分のパターンに持ち込むためのトークなのだが。ミルキィさんのデザインはその対極にある。読んで、ポイントを掴んで…その掴んだところで揺るがないところが素敵だ。ああも読める、こうも読めるという感じではなく。これ!って決めたら、そこを中心にぐいぐい作っていく。でも編集さんとの関係で、変更するフレキシビリティもある。製作費の関係でできないこともたくさんあるから。そのミルキィさんの掴みがそんじょそこらの批評家より深いのが凄い。
update2008/05/16
books
なんでそんなに考えるのか?『ブックデザイン ミルキィ流』

こんなに考えるデザイナーはいない。
デザインは感覚的なもの、感覚が優先する仕事だと思い込んでいる人も多い。
確かに感性は必要だし、最後にものを言うのはセンスだ。しかしセンスを生かすためには、考えること、考えて、考えて工夫をしたりすることが必要だ。今はDTPになっていることもあり、工程が複層化しているし、一人でフィニッシュできない。製作するには、ふさわしい流れを作り出すコミュニケーションも必要になってくる。
エディトリアルというのは、そういうことだと思う。ミルキィ流・ブックデザインの大半は、エディトリアルに費やされている。この本は、デザインの本でもあると同時に、エディトリアルの本でもある。ブックデザインとは、広義のブックマネージメントなのだ。コストのことも計算しなくてはならない。
大好きな割烹の花板さん、三津川等さんの喋りを思い出した。腕が良いだけなら20代でも祇園の花板になれそうだけど、腕だけじゃここに立てないんだよ。今日の仕入れにいくらかかって、今日のこのお刺し身一切れのコストはいくらかって、瞬時に分らないと駄目だし、お客さんのお腹の容量はぴったり把握できないと駄目。親子がそれぞれ彼女を連れて別々に入ろうとしたら、どう対応するのか、酔っぱらっているお客さんには何をだすのか、僕みたいに素面で食べまくっている人にはどうするのか? そんなことがすらりとできないとここには立てない、と。
同じようなことが本をデザインする人にも必要だ。このくらい売れそうだから…でも出版社はそこまで売れるとは思ってにないので、予算はこの位しかでない、紙はコストを下げるけれど、ここにはコストをかけてもらって、それでデザインの意匠を通す…そんなことあんなことをミルキィさんは、にこにこ笑いながらやっている。明るくポジティブに対応するというのも大事な仕事なのだ。
問題は山積みだ。それをひとつずつ考えてポジティブに解決していく。
内容も読む。把握する。この本に書かれている『この本へのアプローチ』というミルキィさんのデザインする本に対する考えが、そんじょそこらの評論より抜きんでている。
考えるという論理的な行為を、感覚的なイメージの世界へ融合させるのは、難しい。そんなことできている人を殆ど見たことがない。現代美術でも考えが進んだ作品は、どこか理屈っぽい。感覚的な作品は思考的な深みがなかったりする。論理と感覚が同時に深い、そしてきちんと整合しているというのは、とてつもなく凄いことだ。
この本を身体を任せて読んでいると、ロジックからポンと感覚に変わるポイントが分るようにもなっていて、本の文体自体が、ミルキィさんの作業生理に非常に似通っているものになっている。読み物としても、教本としても、そしてこうあって欲しいという、表向き語られていない、そして深いところで願い続けている、創作の動機を伝えるメディアとしても、この本は優れて、楽しい。
本ってこういうものなんだな…。本ってこうやって愛情をかたむけて作るもんなんだな…。つくづくそう思う。
update2008/05/16
books
『海の闇、月の影』『天は赤い河のほとり』篠原千絵

理想のコレクター
恋月姫さんと篠原千絵さんの対談がパラボリカビスで行われた。
篠原さんは『海の闇、月の影』 『天は赤い河のほとり』
『闇のパープル・アイ』
などの少女コミックの作家さん。
二度も小学館漫画賞を受賞している。
ストーリー展開に独特の力量があって、どうまとめるんだろうか? どう展開するんだろうかという難しい局面で、例えば伝書鳩が出てきて、パラレルに走っていた話が、一気に統合され、またそこから拡がっていくというような、緩急、幅の広さの自在さに長けている。超能力や不可思議な力がでてくるが、物語の展開に利用されていずに、最小限度、ストイックに使われていて読みやすく、楽しみやすい。物語の筋に妙味がある。
その篠原さんは、恋月姫さんの人形を多数コレクションしている。
そのコレクターならではのお話をいろいろしていただいた。そして恋月姫さんとの対話が面白かった。人形作家さんの側からの感覚と、コレクターさんの感覚と、微妙に異っていて、シンクロしている。
篠原千絵さんは、恋月姫さんのお人形を次の世代に伝えるために無垢のままで持っていたい、だから名前もつけていないとおっしゃっていた。
コレクターさんは、所有しているものに対して、自由を持っているけれど、例えば、ゴッホを125億円で、ルノアールの119億円で落札した日本製紙の齊藤 了英が「俺が死んだらゴッホとルノアールの絵も一緒に荼毘に伏してくれ」と発言して欧米からバッシングを受けたように、なんでも、どうにでも出来るというものではない。文化遺産として伝える義務ももっているのだ。預かっている、伝えるという感覚をどこかにもっている必要がある。というか、そういうものだ。コレクションというのは相応しいところにあるのが、幸せというものだ。
篠原さんは会場にいても、本当に恋月姫さんの人形が好きだ、という感覚が伝わってくる。まず好き、というのがコレクターのはじまりだろう。そいういう意味でも篠原千絵さんは、理想の人形コレクターの一人だと思う。お話を聞けて良かった。
update2008/05/11
books
『闇のパープル・アイ』 篠原千絵
篠原千絵さんが夜想ギャラリーに来訪される。
『闇のパープル・アイ』は、ヴァンパイア譚ではないけれど
血がモチーフになって物語が進んでいく。
純愛なところが女性作家らしい[血族]作品。
なぜ、篠原千絵さんが恋月姫さんと対談するのかは会場でのお楽しみ。
update2008/05/01
books
『禽獣』 川端康成

昭和十年、新進気鋭のダンサーたちが、次々と作品を発表していた。
高田せい子、崔承喜、江口隆哉、エリアナ・パヴロバ、そして石井漠、石井小浪の石井漠舞踊団。そして石井漠舞踊団の新進気鋭のダンサー石井みどりが、第一回創作舞踊発表会を日本青年館で開催すれば、その三日前に石井小浪が日比谷公会堂で新作舞踊を発表している。二つの舞踊雑誌が創刊される。
翌年の昭和十一年、石井みどりは独立公演を行い、石井小浪、高田せい子、崔承喜、江口隆哉、エリアナ・パヴロバは、前年同様、新作を発表している。日比谷公会堂は踊りの会で賑わっていた。石井小浪舞踊団 石井みどり舞踊団 江口・宮舞踊団 崔承喜舞踊団 高田せい子舞踊団が雄を競っていたと思われる。
2・26事件が起きるのは、この昭和十一年だ。
川端康成の『禽獣』が書かれたのは、昭和十年。日比谷公会堂に踊るダンサーとその夫の伴奏弾きが出てくる。石井みどりは、この昭和十年にヴァイオリニストで作曲家の折田泉と結婚して独立している。
余り良く描かれていない、ダンサーと伴奏弾き。飼っている禽獣を愛でながらも次々と育てそこなって殺してしまう、そして場違いな治療をする、そして死んでしまうとぽいっと棄ててしまう、残酷で利己的な私が出てくる。その禽獣にダンサーを重ねて描くという作品だ。
三島由紀夫が、本人が否定して、そこに本質が顕れると言っている、二つの作品の一つが『金色の死』でもう一つが『禽獣
』である。『金色の死』は失敗作だが、『禽獣』は名作だとも言っている。
どうかな…。
update2008/04/23
books
『金色の死』谷崎潤一郎 1914(大正14)

谷崎潤一郎が自らの手によって全集から抹殺していた作品がいくつかある。
三島由紀夫が谷崎の死後、復活させた。『金色の死』。三島の生き方に影響を与えた感のある作品。そして江戸川乱歩が狂喜して『パノラマ島奇談』を書くきっかけになったと言われているいわくつきの作品だ。
今は講談社文芸文庫で簡単に読むことができる。解説を読みながらいろいろなことを考えてしまった。
それにしても岡村が築いた『絢爛なる芸術の天国』のパノラマは、まるで安っぽい個人美術館のような模造品の羅列でしかない。実はこの風景は私たちにとってディズニーランドやUSJの粗形というべき見慣れたものだ。近代において芸術や美がオリジナルの威光(アウラ)を消失して副製品たらざるをえない宿命を1936年に番屋民が唱えるより20年以上早く、ここにはアウラなき模造の美に殉じた人間が描かれていたのである。さらにエドガー・アラン・ポーを模した筆名の江戸川乱歩に、この作品が衝撃を与えて『パノラマ島綺譚』を書かせたのは大正15年(1926)年になってからである。その振る舞い自体が皇軍諸侯の模造であった三島の自死に到るまで、『黄金の死』は模造の循環と連鎖を発動している恐ろしい予言的な作品をいわざるをえない。(清水良典)
+
解説では、谷崎の描く庭園を模造品だと言って、ちょっと否定的だが、逆に、人間にとってのユートピアや楽園や庭園や廃虚を、オリジナルや自然そのもの、いわゆる本物で作るということはあるのだろうか。
++
人工物だからこそ、理想郷になるのではないだろうか。アートとはアーティフィシャルなもの、人工のものである。谷崎潤一郎は、作品の中で…そしてこの作品の元になったと言われるポーの『アルンハイムの地所』『ランダーの別荘』にも繰り返し語られているように、自然は不完全だ、人工的に配置されたものこそ完璧だと語っている。
その例に上げた人工物がどうか?ということは若干あるだろう。江戸川乱歩と谷崎潤一郎とでは、そしてこの作品を強くとりあげた三島由紀夫もまた『癩王のテラス』で人工庭園を描いた。しかし三者とも異る。
そこが面白いのだが、では庭園に並べた美術にセンスがあったかというとそれは、どうかな…という感じだ。それでも、それだからこその理想郷、理想庭園なのだ。
+++
オリジナルの作品をその国の背景や文脈から切り離して蒐集して並べたとしたら、そのほうが俗悪である。本物だからアウラがでるなどという妄想をいい加減棄てた方が良い。オリジナルからでるアウラはあるシチュエーションによって起きるのだし、受け取る側に見とる力がなければ発生しないのだ。そして本物でなければ、いきなりキッチュな模造品だという感覚と美の短絡も改めた方が良いのではないだろうか。
三島由紀夫は『金色の死』の前半に描かれた岡村を自らに投射したのだろう。そして、三島としては余り評価しない後半の部分、白亜の屋敷、ロダンの肉体、ギリシャ彫刻…その模倣。黄金の自尽すらも重ね合わせた。僕の最も好きな三島由紀夫『癩王のテラス』の美学にも通じる原点がここにある。
『パノラマ島綺譚』丸尾末広≫
『アルンハイムの地所』『ランダーの別荘』
update2008/04/20