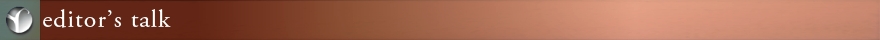books
『パノラマ島奇談』 江戸川乱歩 1926年10月~

肉塊の滝つ瀬は
ますますその数を増し、道々の花は踏みにじられ、蹴散らされて、満目の花吹雪となり、その花びらと、湯気と、しぶきとの濛々と入り乱れた中に、裸女の肉塊は、肉と肉をすり合せて、桶の中の芋のように混乱して、息もたえだえに合唱を続け、人津波は、あるいは右へ、あるいは左へと、打ち寄せ揉み返す、そのまっただ中に…(パノラマ島奇談より)
+
『パノラマ島奇談』に具体的なパノラマ記述は少ない。当時、江戸川乱歩は猟奇的、エログロの書き手として望まれていて、これでもおとなしすぎる表現だったのかもしれない。
++
角川文庫の後書きで渋沢龍彦が、乱歩にはインファンティリズム(幼児型性格)が見られると書いているが、どんなものだろうか。徹底した俗悪ぶりとあるのには、うなづける。
+++
それにしても『パノラマ島奇談』どうも文脈が上手につながっていないような気がする。イメージの上でも…。北見小五郎が出てきて突如、パノラマ島は崩壊するのだが…どうも物語を終える装置として北見小五郎を出してきているとしか思えない。荒唐無稽な話であっても、いや荒唐無稽な話だからこそ、なぜ、小五郎が菰田を追いつめるのかというのは、描いて欲しい。『屋根裏の散歩者』でも明智小五郎の謎解きは文脈として絡んでいない。終わるために終わる設定だ。
++++
壁に塗りこめた千代子の、髪の毛の件も、ポーからの引用なのだが、唐突すぎる。もう少し伏線なり、他の隠し方でなく壁に塗りこめてしまう性癖というものを見せてくれないと。ああ、この主人公なら壁に塗りこめるよな…というイメージの流れ、必然性が欲しい。ポーの小説が怖いのは、そこにに到る人間の深層をひしひしと垣間見せてくれることだ。『パノラマ島奇談』は、ポーの『アルンハイムの地所』『ランダーの別荘』を下敷きにしている。谷崎潤一郎の『金色の死』にもたぶんインスパイアーされている。
☞
update2008/06/01
books
『屋根裏の散歩者』江戸川乱歩 1925

奥山茶屋側の十二階があったあたり
30年ほど前に、カメラをもって彷徨い歩いていた頃はひょっこり侏儒のカップルが目の前を通っていったりした。
だけどそれは違和感のない風景で、とりたてて何かをする気にもならなかった。改めて探して見ればネガの中にそんなカップルが写っているかもしれないが…。
十二階にインスパイアーされて書いたという『屋根裏の散歩者』は、塔から覗くのではなく、下宿館の屋根裏から殺人を犯そうとする三郎の話だ。読みながら思い出したのだが、自分の家も北鎌倉の古い家で、趣味で押し入れに寝起きしていたことがある。そして同じように押し入れの一番端の天井板は簡単に動かせて、そこから天井裏へ入ることができた。電気工事や屋根の補修のための入り口というのもまったく同じであった。
天井板は薄く乗ったらばりばりと壊れてしまう。梁を歩く他はない。ネズミの足跡がたくさんついていた。
『屋根裏の散歩者』の面白さは、三郎の心理を一人称で書いているところであり、事件を解決する明智小五郎は、犯罪者が犯罪がばれてしまったときに陥る、茫然とした感じを描きたいがための設定である。妄想の変態から、ふとしたことで実行にうつし、それがばれてしまう心理を描いている。かなり面白い作品だと思う。
++
変態度をアピールするために、明智小五郎と郷田三郎が犯罪話をするシーンがあるが、そこに出てくる子どもを殺して養父のハンセン氏病を直そうとした、その実、養父を殺した野口男三郎や、小酒井不木が書いたウエブスター博士のこととかが、当時の猟奇流行を反映していて興味深い。
+++
妲妃のお百とか蠎蛇お由だとかいう毒婦の様な気分で…と郷田三郎がひとりごちする。妲妃のお百と蠎蛇お由は、三代目田之助が得意にした出し物で、現代では澤村宗十郎さんが国立劇場で、復活上演された。さらっとこのあたりを書く乱歩である。
毒婦は、悪婆ものと言われていて、悪婆とは役柄の名称で別に歳をとっている設定になっている訳ではない。美しい女形が汚れるというのが良いところで、当代で言えば玉三郎さんだろう。玉三郎さん実際にそうした自虐的な役で妖艶に煌めいて見せる。
宗十郎さんは、シェークスピアで言う阿呆の役ができる方で、大らかなユーモアの演技力は比類ないものだった。宗十郎さんの悪婆もまた素敵な演技で、悪さを感じない、それでいてどんどん逸脱していく破天荒さを出されていて、これまた澤村宗十郎ならではの芸だった。
update2008/05/29
books
『水晶の卵』H・G・ウェルズ 1987年
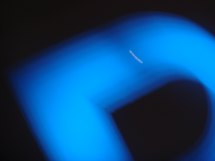
卵の向こうに火星が見える。
現在、火星では、探査機「フェニックス」が生命体の可能性を探している。火星に生命を見たい地球人の願望は、今にはじまったことではない。ヴィクトリア朝の19世紀末イギリスでも、火星に宇宙人を妄想した。
1897年にウェルズは、骨董商の店先にあった水晶の卵を通して、火星を見ていた。ちょうどスカイプを使って火星人と顔を合わせる感じだ。『水晶の卵』は『宇宙戦争』の1年前の作品である。
水晶の彼方に月が二つ見える。高いところから全部を眺めて見たい。そんなことを書いて、火星を感じさせる。
ウェルズはSF作家と言われているが、僕にはどちらかというと幻想的な作家のように思われる。火星が見えるというアイデアも素敵だが、夜な夜な卵形の水晶を覗き込んでは、天使のような姿が見えるなどいう、鉱物嗜好、そして鉱物の中に宇宙が拡がっているという幻想小説の原点のような感覚を好ましいと思う。文学としての筆致がありアイデア倒れしていないのがお気に入りだ。
update2008/05/28
books
『モロー博士の島』H・G・ウェルズ 1896年

モンスターもので好きなのは『フランケンシュタイン』と『ドラキュラ』そして
『モロー博士の島』(H・G・ウェルズ)だ。
書かれたのは1896年。ブラム・ストーカーが『ドラキュラ』を完成させる1年前のことである。この時代の作品はそれぞれに背景があって面白いが、背景にはダーウィンの進化論がある。主人公のプレンディックが、T・H・ハクスリー教授に生物学の講義を受けたと語るところは、まさにウェルズのそのままであり、ハクスリーは「ダーウィンのブルドッグ」と呼ばれたダーウィン進化論の論者であった。論争が好きでないダーウィンに代わって論争を一手に引き受けたのがハクスリーで、ウェルズは、彼に進化論をたたき込まれた。その進化論がウェルズの小説に色濃く影を落とす。
まさに影なのは、進化して素晴らしい人類ができるという方向ではなくて、人すら野獣に戻るかもしれないという進化論の退化可能性のほうに影響を受けているからだ。
+
ジョン・ハンターという名前も出てくる。ハンターは、18世紀の解剖学医であり、ここではキメラをや動物から人間を作るモローの技術的イメージの背景として使われている。
++
面白いのはモローによって一旦、進化した動物が、人間になって、また再び退化していくというところだ。ダーウィンの進化論は、神学に大きな打撃を与えたと同時に、退化もまたあるのだという恐怖である。物語は、モローの島からロンドンに帰った、プレンディックが、自分もまた野獣に退化するのではないかという怖れをもって、秘かに研究に生きるところで終わる。
update2008/05/28
books
『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』 石井輝男

『パノラマ島奇譚』のタイトルで映画やテレビドラマになっているものはあるのだろうか。
テレビドラマの明智小五郎シリーズで、原作を『パノラマ島綺譚』にしている『天国と地獄の美女』はある。あとは、石井輝男の『江戸川乱歩全集 恐怖奇形人間』が、『パノラマ島奇談』と『孤島の鬼』をベースにしている。大筋の原型は『パノラマ島奇談』からとっているが、あくまでも土方巽扮する、菰田丈五郎が、人工的に奇形を生み出し、自分の奇形を嫌悪した妻に復讐するという畸型譚になっている。
土方巽の海岸での踊りを観ていると、大野一雄に振り付けたような形も見え、脈々と暗黒舞踏を流れているものが何かということがひしひしと感じられる。芦川羊子の姿や、火と人間を同じようにしてぶん廻す白虎社の面々も踊っているし、島のシーンはとてつもなく懐かしい。この映画の前年、土方巽は『肉体の叛乱』を上演している、中で使われたシーンやセットが出てくるのが、ぐっとくる。踊っているところは、しっかりと踊っている舞踏手たちの若く、荒々しい見得が素晴らしい。
最後、ややそれまでのトーンとは異って、荒唐無稽に花火とともに薦田と千代の首や手が、宙を浮游するが、これは乱歩の『パノラマ島奇談』のラストからそのままもってきたイメージだ。