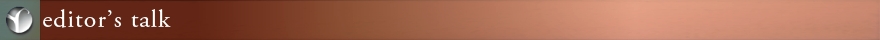column
勅使川原三郎アップデートダンス「春と修羅」

勅使川原三郎のアップデートダンスNo34。今回は宮澤賢治の「春と修羅」、アップデートダンスは、日々刻々変わっていく。本当に変わっていく。それは作品を作り上げるためのもの、であり、そこに一回きり存在するためのものである。正面から正統的に作り上げることは、芸術にとって必須の行為であるが、実験と今と未来を含んで作る時、それは意外と出来上がらないことが多い。その過程の中でどうしようもなく逸れたり、ユーモアがでたりする、派生のところに究極の表現がひょっと顕れたりする。そんなことを勅使川原三郎は無意識に本能的に狙っているのかもしれない。
今夜のダンスは、これ一回きりのもの、明日にはまた変わっていく。このシリーズも勅使川原三郎のソロで始り、今は佐東利穂子とのデュオになっている。
勅使川原三郎は、今ここで佐東利穂子とダンスで対話をしながら踊っている。相手の動きに応じて踊っているパートは、果たし合いのような緊張感がある。それでいて感覚は限りなく自由な時空にいる場合もある。二人は本番の中で、作るリハーサルをしているような不思議な境地に達している。
アップデートダンスは、見せるダンスというよりは、ダンサーがどう踊るかに主眼が置かれている。
それでも、もともと見せること、空間の演出に長けている勅使川原なので、どこかに何パーセントか見せるという要素がある。観客の前にたちその呼吸の反応は明らかに反映しているのだから。
見る人たちをぐいぐいと惹きつけていく。優れた絵描きのデッサンが出来上がった絵画より見るものに別の魅力をもっているように。それをグリザイユと絵画では言うが僕は個人的にずっとずっとグリザイユを求め愛してきた。
宮澤賢治の「春と修羅」は詩的な言葉で綴られているが、勅使川原はそこから醸し出される詩的なイメージを使うのではなく、その詩の言葉自体に向かっている。しかも限りなく具体的に対峙している。勅使川原のダンスが、詩の言葉になり、詩を生み出す装置にもなっている。宮澤賢治と勅使川原三郎がともに「春と修羅」を詠んでいるかのような印象だ。
勅使川原三郎は、だいぶ前に、宮澤賢治の詩『原体剣舞連』を元にダンスを創作した。一緒に種山高原に行き不思議な体験をした。その一部が写真に残っている。
その時、宮沢賢治に向かっている時と大きく異なっているのは、死という要素を身近に置いていることだ。「春と修羅」から死の具体を糸として抽出して織りなしている。勅使川原の踊る「春と修羅」は、死と生のダンス、その交錯を描いている。ラスト近く、勅使川原三郎自身が朗読する声で踊るシーンは、死を迎える心の柔らかさと、それを受けとめる身体の痙攣が重なり合っている。
update2016/06/22
column
森村泰昌Ⅰ

森村泰昌
横浜トリエンナーレの最後のパフォーマンスで、あ、カフカを忘れたなどと呟いていたように記憶しているが、そのカフカの作品の元になるエスキースがパラボリカにある。森村泰昌アナザーミュージアム@ナムラには撮影に使った羊がもう船の入らないドッグを見ていた。
update2016/04/09
column
押絵と旅する男
押絵を旅する男/江戸川乱歩
朗読 井上弘久 美術 日野まき

乱歩と潤一郎の版権が今年切れる。青空文庫では一斉に解禁になるだろうし、一方、詳細な研究の進んだ谷崎潤一郎の全集の刊行も進行している。
そんなこともあってか、ないのか、茶会記で乱歩の朗読会を企画することになった。茶会記は四谷にある喫茶バーでイベントもする。
茶会記は羨ましいほどに言い名前だ。
作を選ばせてもらうなら、「押絵と旅する男」。自分としてはこれ。人形繋がりということもある。夜想の「カフカのよみ方」で体得した本のよみ方その一。自分の得意ジャンルからの視点で入る。
僕で言えば、踊りとか人形とか。他の人のカットインに乗るという方法もある。贅沢な感じで髙橋悠治のピアノを弾く指とか。もちろんピアノや音楽に素人な自分では、乗り切れないけれど、目の前が開けるような視点をもらえることもある。
押絵を旅する男 Ⅱ
2月13日、14日にパラボリカ・ビスで再演するのだけれど、日野まきの美術が朗読をブローアップしている。乱歩の「押絵と旅する男」の挿絵でもあり、井上弘久の朗読演劇の美術でもある。
挿絵といえば、小村雪岱。「一本刀土俵入」の取手の宿の舞台装置の鏝絵で六代目菊五郎を喜ばせ、台詞が美術作品に及んでいる。昔のコラボレーションは粋に満ちあふれている。自分を主張するのではなく、コラボレーションして出きあがるものに対して情熱をかけているのが素敵だ。
ともあれ人形で「押絵を旅する男」を読むと兄さんと弟の感情の交錯が見て取れて面白い。視点をどこに置くかで隠れているものがでてくる。
「押絵と旅する男」は、乱歩の覗き見趣向、レンズ嗜好がからくり箱にしっかりと嵌まった名作だけれど、今回、朗読を手伝っていて気がついたのは、「ピントがあう瞬間」の魅力だ。
押絵を旅する男 Ⅲ
乱歩は、中学生の頃、部屋に閉じこもりっきりになって雨戸の節穴から差し込む光を見ていたことあがあり、それを自分では憂鬱症と言っていた。差し込んだ光が天井にもやもやを作り、それに驚愕して慄いていたがしばらくしてその正体を発見する。(「レンズ嗜好症」)
何だか分からないものにピントがあって像がくっきりする。その瞬間のゾクゾク感、それが乱歩のレンズ嗜好なのだ。「押絵を旅する男」は、態々魚津へ蜃気楼を見に出掛けた帰り途であった。私によって書かれているが、相変らずの癖というか文体で、これは乱歩自身のことである。不用意に小説の中に出てくる乱歩のその有り様を愛でる中井英夫が分かるようになったのも、今回の大きな収穫であるが、それはともあれ、蜃気楼、遠眼鏡のピントが合う瞬間の魅力が乱歩の囚われていた書くことの魅力の一つだろう。押絵がなんだったというユリイカの瞬間とその設定が、乱歩の書く醍醐味だったのではないだろうか。
update2016/01/24
column
賀川洋様への謝罪文
謝罪文
エディターズ・トーク http://www.yaso-peyotl.com/archives/et/002758.htmlにおいて、2004年青山ブックセンター倒産から、2008年の洋販倒産までの経過を、体験以外の部分を、ネット上の資料や記事を使って書きました。事実を確認する補足取材することなくそのまま7年間放置してしまいました。そのためIBC パブリッシング代表・賀川洋様に、ご迷惑をおかけしました。心よりお詫び申し上げ記事を削除します。今後、このようなことがないように、地に足をつけて真摯に取材をして文字を使っていきたいと思います。大変申し訳ありませんでした。
2015年9月20日今野裕一
update2015/09/04
column
未来をなぞる写真家・畠山直哉

この映画の中でしか見られない畠山直哉の写真がある。
畠山が写真に向かっている姿、過程、考え続けている思考、この映画の中でしか見られないものがたくさんある。
デビュー前から畠山直哉の写真を見ていて、時々、話もして、何回か自分のトークにも来てもらっていた。畠山直哉の写真をある程度、把握できると思っていた。
でも映画の中に出てくる畠山直哉の写真は、僕にはすぐに把握できないものだった。
写真について言えば、例えば独特の構図、対象の見方、距離……、そうしたことは、作家が作家になったときから大きくは変わらない。それがその作家の作家らしさということだから。写真の対象への距離がきちんと一定していること、向かい方ということも含めてだけど。その距離感がその作家の個性である、なんて言い方もある。
だから写真美術館で「Natural Stories ナチュラル・ストーリーズ」を見たときに感じた、写真の変化、そして畠山直哉と交わした言葉を聞けば、変化するだろうけど、ゆったりと、かみしめるようなものなんだろうな、と、思った。
写真がもってる枠組み、特にそれが美術館の中で展開されるようになった後の写真の枠組み、それを含みながら作家がそこで確立するもの、それが写真だった。(もちろん写真のすべがそうではない。写真は多様に存在する)そんな枠組みを含めて、あるいは、それを利用して作品と作家を見ていたわけだけれど、そんな見方を含めて………写真というもの……そういった写真にまつわるいろいろが、畠山の中で崩壊したんだ。そして彷徨しているんだ。変化は、根底を揺さぶるような激しいものだった。それが映画の中に写っている。
震災の後、畠山直哉と、一度、話をしている。震災の後、陸前高田の刻々変わる風景、そして何もなくなった。縄文時代のようだよ。彼はそう言った。それが進化するのに、元にもどるのに果てしない時間がかかる。写真の歴史はたかだか200年、何もなくなった故郷、陸前高田で自分は、写真で何ができるのか。とも。
畠山直哉が向きあっている陸前高田は、ゆっくりと考える時間を畠山に許してはくれなかった。更地のようになったところに、土が盛られ、山が削られ、そしてそれを移動するための巨大な橋が造られたり……。畠山の思考の変化は、変化という言葉では生易しく、動乱、迷走、彷徨、そんな言葉が必要なくらい揺らぎ、虚ろい、苦悩していく。
向こうから来た圧倒的なものに向かい続ける畠山直哉。自然の災害、その跡を処理する政治、起重機、ダンプ…故郷は激変していく。畠山は、それを受けとめきれない、そう誰も受けとめきれないのだが、畠山は写真と写真をする思考で、それに向かいあう。それの不可能性を受けて心にとめている。
このドキュメント映画にはそういうことも写っている。
ドキュメント作家のには申し訳ないが、この映像は畠山直哉の写真であり思考であり、そして苦悩の変化である。畠山の行為をじゃませず、それを丸々写している。カメラの前で畠山直哉は苛立っていない。(取材しに来た海外のジャーナリストに彼は密かに苛立っている。)写っているものを邪魔しないドキュメント作家というのもいていい、あってもいい。演出だって主張する演出と、手を見せない演出がある。
この映画のトーンが何かに似ていると思ったのは、映画館を出た時だった。畠山直哉は、大学を出てすぐに「ボイス・イン・ジャパン」というドキュメント映像の編集をしている。撮影クルーがそれぞれに撮ってきた、かなりの量の素材映像を、一時間にまとめる仕事をした。若かった。20代の前半だろうか。ボイスがある種の熱病的なブームの中で、迎えられた中で、畠山直哉の編集の手だけが静謐だった。その静謐さを思いだした。騒乱の中で彼の写真は静かだ。その静けさは、美のように観客には写るのだろう。
畠山直哉の写真は、この2年の中で、畠山直哉独特の構図や視線を取り戻しつつある、ように見かけは見える。それはかなりの驚きだった。
ロマンティックなたとえ話にすれば、写真の枠組みとか写真を写真足らしめているものを根こそぎ流されて、写真の縄文時代に戻って、それがまた次第に現在の畠山の思考を反映する写真として形成されていく。その過程が、このドキュメント映画に写されているということになる。
しかしことはそんなに単純ではない。今、見れば、震災の直後に撮られた写真にも、震災以前の畠山直哉の写真が生きていて、しかし、それは2年位前に見たときにはそうは見えなかった。ブラストのような圧倒的な写真群を頭に記憶している自分には、等身大の、視線がぐっと低くなった別の写真のように見えた。しかし震災後の写真の量が増え、写真集が出版され、ドキュメント映画が公開されると、劇的に変化しているものの中で(風景、畠山の思考)写真はその劇性を反映していないように見える。(それが畠山直哉の写真なのだ)写真は化学だから、心が写らないものだから。
畠山直哉が映画の中でも言っているように、震災前にスナップのように撮っていた故郷の写真は、今、まったく意味が変わってしまったと。写真は、見る方によっても、提示によっても、文脈によっても変化する。陸前高田が変われば、畠山直哉の写真も考えも変わる。その変化の中で、見る方の変化もある。
この写真はこういうものだ、という安定した見方はもうない。表現している内容を固定して記述することができた幸せな時代は終焉している。おそらく。対象と表現者と受け手と、そのどれもが浮浪している。変化している。定まった形式をもてなくなったのだ。「うつろい」がその三者に纏わりつく。暗鬱をもって。
そんなことをこのドキュメンタリー映画は映しだしている。
update2015/08/24
column
畠山直哉

update2015/08/23
column
お茶の時間。

手揉茶 飲んだことない味。
カフカノートを朗読する。可能か? 可能にしたい………。
悠治さんは、きっと言葉に音をつけないんじゃないの。言葉と音をそんなふうな関係に置いてないかも。と。 指から言葉が入ってきて、身体に入って
………。悠治さんはここにいないのに、悠治さんを思いながら話している人たち。 リスペクトを越えた、理解というのか、共闘というのか。お茶を前にしてそんなことを思いだし。「カフカ、夜の時代」を読む。カフカと病と夜の時間を共有しながら悠治さんは、身体の中を通っていく時間とか、夜とかを息していた。
update2015/07/29